植栽計画書は、樹木の種類や配置を可視化して景観と機能を両立させる重要な設計資料です。
CADデータを使えば、2Dと3Dで成長後の樹形や日陰をシミュレーションでき、関係者間でイメージを共有しやすくなります。種類選定や植える目的、維持管理ポイントを押さえて、環境と美観を高める計画を立てましょう。根張りと成長も確認でき安心です。
このページでは、植栽計画と樹木CAD活用法について解説しています。
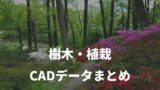
植栽計画書はCADデータの活用でこんなに変わる
3Dのデータを活用すれば、どんな設計になるのか施主にわかりやすく伝えることができます。
さらに、施主との会議中に変更点が生じた場合にも、CADを活用した計画書であれば柔軟に対応することができます。
樹木は、年月経過によってメンテナンスが必要になります。
CADデータでは、経年変化のシミュレーションも行うことができるので、植栽には欠かせないツールだと言えます。
樹木の特徴を生かし最適な植栽計画はCADデータでチェック
植栽を上手に行うためには、目的や用途に応じた樹木を選ぶことが大切です。
それぞれの樹木の特徴を生かした、最適な植栽を行いましょう。
・クスノキ、シラカシ
クスノキやシラカシは、高木の常緑樹です。
そのため、強風や雪防止に大きな効果があります。
・サザンカ、ヒイラギ
サザンカやヒイラギは、含水量が多く、葉肉の厚い常緑樹です。
そのため、火災の延焼などを防ぐ効果があります。
・アベリア、ベニカナメモチ
アベリアやベニカナメモチは、美しい季節の花々を付けることで有名です。
そのため、道ゆく人に季節の花々を楽しんでもらうことができます。
・コナラ、アメリカハナミズキ
コナラやアメリカハナミズキは、高木の落葉樹です。
3m~4mの高さになるので、住宅や街のシンボルとして活用できます。
・ライラック、エゴノキ
ライラックやエゴノキは、葉色が美しく変化し、四季の移り変わりを楽しむことができます。
そのため、街並みを彩る街路樹として人気がある樹木です。
・ウバメガシ、モクセイ
ウバメガシやモクセイは、肉厚な葉肉が特徴的です。
家と家の間などを埋め、プライバシー保護に役に立ちます。
・ヤマボウシ、ヒメジャラ
ヤマボウシやヒメジャラは、落葉の高中木です。
夏には爽やかな木陰を、冬には暖かな日差しを作りあげることができます。
・キンモクセイ、ツバキ
キンモクセイやツバキは、香りが豊かな樹木です。
それだけではなく、隣地からの覗き込みを防ぎ、プライバシーを守ってくれます。
上記のように、樹木によって特徴が大きく異なり、用途も変わってきます。
CADデータを活用して、用途に応じた樹木選びを行いましょう。
今回ご紹介しているサイトでは、dwg(autocad)・dxf・jww(jwcad)・ベクターワークスなどさまざまな拡張子があるので、何かしらお探しのデータが見つかると思います。
そこで、このページでは、樹木、植栽、植物のCADデータの特徴とリンクをまとめて紹介します。
建物や駅などのCADデータを作る場合、樹木はほとんどのパースに関わっています。
樹木をパースに配置する際は、種類や植える場所だけではなく、経年変化についても考えておくと、よりイメージをしやすいパースとなるでしょう。
その場合、CADは欠かせないものとなります。
樹木の種類、場所、大きさなどを、すぐに変えることができるからです。
そのため、樹木などの植物のcadデータは、様々な種類のものを必要としています。
しかし、3DCADと2DCADでは少し求められるものが変わってくるため、詳しく考察していきましょう。
樹木(植栽・植物)テーマのCADデータは3DCADと2DCADで違った特性を持つ
それではまず、樹木、植栽、植物のCADデータを使うときの留意点、3DCADと2DCADの違いによる、イメージに合ったCADデータの使い方について説明しましょう。
平面図での樹木パースはイメージがわかりにくい
2DCADの平面図で樹木を配置すると、円形に表示され、立面図と違ってイメージがなかなかつかめません。
公園の植え込みなどの場合は、円形が連なり、知識のない人が見た場合は、一見樹木とは思えないかもしれません。
そのため、2DCADの平面図で樹木を書き込む場合は、できるなら、色を付けるなどの配慮があるとわかりやすくなります。
立面図での3DCADと2DCADとの樹木の比較
次に、立面図の場合はどうでしょうか。
2DCADでは、植物か樹木かということはわかりますが、種類まではなかなかわかりません。
また、光が当たったときの影の具合や、樹木の後ろ側など、わかりにくい点も多々あります。
その点、3DCADでは、葉の形状までわかりやすいため、種類の検討がつくでしょう。
それに、光や影の具合、幹の太さ、色まで見して認識可能です。
また、インテリアプラントに焦点を当てると、3DCADならば樹木の種類だけではなく、植木鉢にまでこだわりを見せることができます。
特に、部屋の中に関しては、外観よりも光の加減が重要になってきます。
植物を置くことで、部屋の雰囲気をワンランク上の印象にもっていきやすくなります。
3DCADで植物を配置する、気持ちの落ち着きメリット
3DCADパースの場合は、イラストとして認識している人が多いです。
そのため、大きさよりも植物の種類や光の加減、置き場所などに拘れば、よいパースに仕上がりやすくなります。
少しでも緑があると、人の気持ちは落ち着くものです。
3DCADでパーツを仕上げる際は、植栽を入れておくことで見栄えがして、親しみやすいパースとなるでしょう。
樹木・植栽・植木・低木・高木の3Dcadデータのサイト紹介です。
樹木をCADで描くときは、はじめの樹木のシルエットが重要です。
ここで殆どの形体が決まります。
樹木の明暗を意識して描き、立体感をだします。
細かい部分にこだわらず、樹木全体を描くことが大切です。
樹木・植栽・植木・低木・高木などの、3Dcadデータが、ダウンロードできます。
どんな場所と目的に合わせてどんな樹木を活用するべきか
樹木の使用目的を明らかにする
環境の保全と、日陰のある場所の確保が、樹木を植える主な目的です。
また、建物周辺に樹木があると、建物自体の付加価値も高まりやすくなります。
樹木を植えるときのポイントとは
・ 樹木の生長に必要な厚さの土層は確保できているか
・ 排水性に問題はないか
・ 勾配に合わせて樹木を選ぶ
植栽を行う際には、景観や敷地の境界など、それぞれの目的に適した樹木を選びましょう。
植栽目的によって樹木の種類はさまざま
樹木は、公園や道路、住宅など、さまざまな場所で見られます。
公園における樹木は、市民の生活に、安らぎを与えるために欠かせない要素といえます。
住宅での樹木は、生活に彩りを与え、プライバシーを守ってくれる存在になっています。
それぞれの植栽目的に合った、樹木の例です。
・ 風や雪から建物を防ぐ → 高木の常緑樹(クスノキ、シラカシ、マテバシイなど)
・ プライバシー保護、境界を明らかにする → 常緑樹の針葉樹(スマラグ、ブルーヘブンなど)
・ 火災による火の燃え移りを防ぐ → 厚い常緑樹(サザンカ、ヒイラギ、マサキなど)
樹木のCADデータを活用してイメージのすり合わせを
樹木CADデータの利点
樹木のCADデータを使用すれば、後になって「こんなはずではなかった」ということが減り、完成イメージに近い図面を作成できます。
樹木の位置の把握、高さ、種類など、よりリアルに表すことができるでしょう。
また、樹木の高さや本数などを変更して案を出すときにも、いくつかの樹木CADデータをあらかじめストックしておけば、簡単に呼び出すことができます。
作業の効率アップに繋がります。
ただし、ダウンロードする際はdwg(autocad)・dxf・jww(jwcad)・ベクターワークスなどの拡張子に気を付けてください。
海外サイトの場合はdwg(autocad)ファイルしかない場合も多いので、jww(jwcad)やベクターワークスなどのCadを使用している方は特に注意しましょう。
樹木CADデータの弱点・活用する際の注意点
平面・立面ともにCADデータとして存在する樹木の種類はあまり多くありません。
あくまで樹木の高さ、本数、植える範囲を示す際にCADデータは使用すると良いでしょう。
データを使用する際は、樹木のかたちやイメージにはあまりこだわらず、名称や種類は横に補足として書いておくのが一番です。
樹木のCADデータを活用し植栽のイメージを固めよう
樹木の役割を知っておこう
樹木の役割は、環境の保全や緑化、もしくはプライバシーの保護、敷地の境界などさまざまりあります。
その目的に合った樹木を選ぶことが大切です。
もちろん、dwg(autocad)・dxf・jww(jwcad)・ベクターワークスなどの拡張子を確認することも大切です。
樹木のCADデータを使えばよりリアルに建物のイメージが掴める
樹木のCADデータを使えば、よりリアルに建物の完成図をつかむことができます。
樹木の高さや位置などについて、後になってイメージの食い違いが起こるのを避けることにも繋がるでしょう。
どの位置に植栽するか、どの高さにするか、試行錯誤を重ねるうえでも便利です。
樹木を植える効果、快適性の向上や周辺環境への配慮
樹木の目的、周辺環境の整備と道路環境の保全
さまざまな場所で樹木や植物は用いられ、公共工事で樹木が関わるものとしては、公園や街路樹の整備、公共施設の緑化工事などが挙げられます。
民間工事で樹木が関わるものには、ビルやマンションの緑化工事、住宅の造園工事などがあります。
公園は市民の憩いの場であるとともに周辺環境の整備という目的があり、街路樹には道路環境の保全と歩行者に日陰を提供するという目的があります。
住宅やマンション、ビルの周辺に樹木を植えることで、居住者の快適性の向上や周辺の環境への配慮、建物の付加価値を高めるといった効果が期待できます。
樹木を植栽するときのポイントを考える
ビルやマンションの植栽を行う際は、植物が育つために必要な厚さの土層を確保し、排水性に問題がないか確認する必要があります。
また、法面の勾配も考慮し、法面の勾配に合わせて、植栽する樹木を選ぶことも重要です。
植栽には景観はもちろん、それ以外にも敷地の境界、プライバシー保護、風よけ、防音などの役割があります。
植栽目的に合わせた樹木の種類を知ろう
建物の敷地などの境界を分けたり、プライバシーを保護したりするための樹木には、葉があまり落ちない常緑樹の針葉樹、スマラグ、ブルーヘブンなどがおすすめです。
強風や雪を防止する目的で樹木を植栽するなら、高木の常緑樹、クスノキ、シラカシ、マテバシイなどを選びます。
騒音を緩和する目的なら、下枝が低く、枝葉が密になる常緑樹を、さまざまな高さのものを混ぜて植えるといいでしょう。
火災の延焼などを防ぐ目的なら、含水量が多く葉肉の厚い常緑樹、サザンカ、ヒイラギ、マサキなどをある程度の広さがあるスペースに植栽します。
樹木植栽ならではのシルエットをイラストやCADデータで描いてみる
樹木植栽について、なんだか難しそうだなと感じている人もいるのではないでしょうか。植木や高木、低木などの種類もありますし、それぞれに樹木植栽を行う方法が違います。初心者にとっては少しハードルが高く感じがちな樹木植栽も、その方法を知っていれば挑戦しやすいかもしれません。植木を始めるうえでの基礎知識も含め紹介します。
樹木や植木の健康状態を上から下までに分けて確認する
樹木の健康状態を確認するためには、植木の上から下までを分類分けして評価していきます。同じように見える樹木でもその部分ごとに状態が違うのがわかるので、植木の元気がない原因を把握することにも繋がります。
樹木植栽の悩み①:剪定部分にコブを作る
樹木にとっては、大きな枝や幹が切られるのは死活問題です。高木や低木などのちがいはなく、今まで植物の生活に必要な物質を作っていた葉が大量になくなります。樹木を少しでも大きくしたいと考えているのであれば、若木の頃から剪定をするのをおすすめします。
若木を切ると、切り口の部分より多くの枝が出てきて次第にコブ状になります。見た目こそいまいちではありますが、病害虫にも対抗できる強いエネルギーを持っています。
ちなみにコブを作らない方法として「すかし剪定」呼ばれる方法もあります。人工的で伏江膳な状態を改善するために、長く大きくなった枝を剪定するときに切り葉を落とす枝の代わりに、枝の叉部を平行に切っていきます。
この方法で得は、葉から糖が切り口の部分に送られるので切り口の癒合も早く腐りにくくなります。花芽分化も支障なく行われるため、毎年新しい花が咲く特徴もあります。
樹木植栽の悩み②:葉の大きさが小さくなる
植木や高木、低木によっても違いますが、元気のない木は葉の長さが短くなります。大気中の環境や土壌の乾燥、根の障害などの理由によって十分に栄養が吸収できないときに、葉を小さくしたり、枝の先端が枯れてしまう原因になります。
葉は植木にとっても光合成を行うなど、エネルギーを作る大切な部分になります。水が少ないのが葉が小さくなる原因です。
樹木植栽の悩み③:胴吹き、ひこばえ
太い幹から小枝が直接生えているとき、眠っていた芽が緊急事態で起こされて出てきたものになります。例えば、上にある枝が病気になってしまい、代わりに栄養を届ける役割があります。根元から出ているものをひこばえといい、幹や枝から出ているものを胴吹きといいます。植木や高木、低木の上の小枝が枯れて胴吹きやひこばえしかない状態は、木が衰えている可能性があります。これらが全く生えない木は危機的状況といえます。
ちなみに松の芽はシンクイムシなどに侵されなければ、必ず発芽して枝になります。松は休眠芽を全く持っておらず、枝が切られるとふさごうとすると癒傷組織がほとんどできません。
その代わりにまつやにを使って傷口を覆います。病原菌が内部に入るのを防ぎ、傷口や枝の痕は幹の成長とともに埋もれていく仕組みになります。松は他の高木や低木とは違った修復の仕方をしている特徴があります。
樹木植栽のシルエットをイラストやCADに描く
樹木植栽ならではのシルエットをイラストに描くときは、平面図や立面図が重要です。Autocadやベクターワークスなどは視覚性が高くインターフェイスに優れています。Cadデータによってdwg、dxf、jwcad、jwwなども違いもありますし、フリー素材の図面なども十分に使いこなしてみてくださいね。
dwg、dxf、jwcad、jwwの変換方法に注意しながら、無料のフリー素材などの図面をダウンロードしてみてくださいね。Autocadは初心者にも向いていますし、ベクターワークスは平面図や立面図などのイラストのシルエット把握にも向いています。
Cadデータの無料ダウンロードを使わない理由はありません。
樹木植栽の枝はとても重要、その診断や手当する方法
樹木にとって高木や低木に関わらず枝もとても重要です。
状況を診断して適切な手当も必要になります。
冬に落葉した枝が生きているのかどうか確認するのは、樹皮を少しはげば簡単に判別できます。枝は独立採算性になり、必要な糖分はその枝についている葉で作られます。そのため、枝は他の枝が作った糖分を受け取ることはできません。
糖分をきちんと作れないと、枝の付け根まで枯らせてしまうリスクもあります。木にとっても光合成の悪い枝から窒素やミネラルを回収していくため、余計に枝の枯れがひどくなります。枝は枯れ始めると早いのはこんな理由があるのです。
夏から秋の時期に欅の木の下に行ったことはありますか?枯れ枝がたくさん落ちているのですが、これはその年に伸びた枝に覆われて光合成が十分に行えなくなった枝を自分で落としていることにあります。欅は枯れて乾燥すると収縮が始まり、まだ生きている部分との間に亀裂を作ってしまいます。少しでも強い風が吹いてしまうと、簡単に落ちてしまいます。欅はもともと自分で枯れ枝を整理する特徴があります。
Autocadやベクターワークスを使って樹木植栽の平面図や立面図を描く
樹木の枝の診断方法も見た目からはわかりにくいものです。Autocadやベクターワークスを使って、平面図や立面図、シルエットなどをダウンロードしてイラストを描いてみてくださいね。
Autocadやベクターワークスはdwg、dxf、jwcad、jwwなどの選択肢も多く、cadデータとしても申し分有りません。無料のフリー素材で図面を選ぶのはもちろん、dwg、dxf、jwcad、jwwの変換方法なども注意してくださいね。
平面図や立面図、シルエットは、cadデータを使うのが一番わかりやすくおすすめです。イラストにしても出来上がりの質が違います。図面のフリー素材や、無料で使えるダウンロードも使いこなしてみてくださいね。
枝が元気か確認する、樹木植栽の上部の枝が枯れているときは要注意
枝が元気な常態かどうか確認する方法があります。例えば上部の枝が枯れているときは要注意のサインになります。春から初秋の頃は葉からも蒸散が頻繁に行われています。
でも根の部分が傷んでしまったり、次が踏み固められて土壌のなかにある酸素が不足したり、水が停滞すると樹木は十分な水分が確保できません。特に高い位置まで運ぶのが難しくなり、葉が小さくなったり枝が伸びなくなったり、葉が少なくなることもあり最終歴には枯れてしまいます。
大気中からの水分を吸い取ろうとする力と、根が土から水を吸い上げる力の釣り合いがとれないと、途中で切れてしまいそれ以上上には水が上がらなくなってしまいます。逆に上の枝が元気で下や中間にある枝が枯れている場合は、日陰になっているのが原因です。木の自然な姿になるので、大きな問題としては捉えません。
関東平野などの大都市になると杉林の上部が枯れてしまうのは、酸性雨や光化学スモッグなどの大気汚染、落雷などの説が考えられています。ヒートアイランド現象によって、平野部は気温が高くなり大気の乾燥を進めてしまいます。
他にも土壌の踏みかためや、舗装、下水道整備、建物の密集などがあり、水が入りにくい環境になっています。
樹木植栽のcadデータを活用して枝が元気かどうかを確認する
枝が元気かどうかを確認するためにも、cadデータを使いこなしてみてくださいね。平面図や立面図、シルエットなどのイラストはもちろん、dwg、dxf、jwcad、jwwなどの違いもあります。Autocadやベクターワークスなども使いこなすと面白く、無料のフリー素材の図面も含め、ダウンロードして試してみてくださいね。
樹木植栽の知識や技術について説明しました。それぞれの特徴やシルエットも、平面図や立面図で見るのかによっても違いますし、イラスト化してみると見えてくると想います。Autocadやベクターワークスの違い、dwg、dxf、jwcad、jwwなどの変換にも注意してくださいね。Cadデータの図面は無料のフリー素材も充実しているので、ダウンロードして使いこなしてくださいね。
平面図や立面図のCADデータ、シルエットやイラストで見る樹木や植栽の力強さ
樹木や植栽は秋になるとなぜ真っ赤に紅葉するのか
秋になると真っ赤に染まる紅葉を、秋の風物詩として考えている人も多いと思います。落葉広葉樹は街中や建物の傍にもよく植栽されていて、シンボルツリーのような役割を果たしている植木といえます。
なぜ葉が紅葉するのか。秋になり寒さが増してくると、樹木は離層と呼ばれる、落葉するための層を葉と茎の間に作ります。その過程で、ミネラルを葉から茎へ移動させ、葉緑体の中にある成分が分解されてできるアミノ酸と、葉に残る糖分が加わって一種の色素が形成されます。それが人の目には紅葉に映るのです。
施設などの設計をするときも、植栽や植木のことを考えて設計する必要があります。cadデータを使えば、図面の共有が容易で、平面図・立面図・シルエット・イラスト関わらず正確に作成することができます。無料でダウンロードできるcadデータや図面を利用するのも一つの手段です。フリー素材にはdwg、jww、dwg拡張子で保存できるものや、加工しても良いものも多くあります。
紅葉する樹木と黄色に染まる樹木の違いって何?
紅く染まる紅葉の他に、イチョウなどのように黄色に染まる樹木もありますね。これは、葉緑体の中にあるクロロフィルという成分が分解されてなくなると、もともと葉の中にあったキサントフィル類の黄色い成分が表に出てくるために黄色く色づいて見えるようになります。成分が結合して現れる紅葉と、成分が浮上して現れる黄葉の差です。
その年によって色づきが変わる樹木の紅葉の仕組み
今年の紅葉は綺麗だった、昨年はイマイチだった…そうして紅葉の見事さが毎年変わる原因は、樹木の健康状態や栄養状態が生き物のように毎年違うからだといえます。その年の夏が冷夏で雨が多かったのなら、葉中の糖濃度が低くなり、秋の紅葉はあまり綺麗にはなりません。一方、雨が少なく秋になって急に寒さがやってくるような年は、見事な紅葉になるケースが多いのです。
植栽には、もちろん日の当たりや風通しの計画も大切です。無料でダウンロードできるCadデータや図面を使えば、フリー素材でautocad(dwg)、dxf、jwcad(jww)の拡張子が簡単に手に入ります。植栽も高木や低木などさまざまですが、必要な平面図・立面図・シルエット・イラストを選ぶことができます。
高木で落葉樹の樹木を配置、落葉で外から窓の中が丸見えになってしまった
樹木にはさまざまな種類があり、中には秋から冬にかけて落葉する種類の樹木があります。例えば設計した窓の傍に配置した樹木が高木で落葉樹だった場合、秋から冬は葉が全て落ちるので、外から窓の中が丸見えになってしまうこともあり得るのです。
cadデータや図面では、様々な植木のデータがそろい、シミュレーションができるようになっています。autocad(dwg)、dxf、jwcad(jww)など、自分に合ったファイルを使用すると良いでしょう。もちろん、フリー素材をダウンロードして無料で利用するのも良いでしょう。
樹木や植栽が落葉する理由は寒さに耐えて身を守るため
葉をつけたまま冬を迎えると、葉が凍ってしまう可能性があります。そんな寒い地方に適応しようとして植木が編み出したのが、落葉という身を守る方法なのです。
落葉樹の中でも、寒さが到来してすぐに落葉する種類もあれば、ケヤキやコナラのように、落葉を春先の新芽が出てくる時期まで待つ種類もあります。そうすることで、小さな冬芽を寒い風などから守っているのかも知れません。
樹木や植栽は日照時間を覚えて落葉する時期を判断する
植木は日の短さで冬の到来を知ります。それゆえ、街路樹で電灯の近くにある植木などは、ときに秋が来ても落葉せず葉をつけたまま勘違いしている木があります。マイナス5度まではこの状態が続き、そのままでは冬への抵抗力が落ちることが検証で分かっています。
平面図で見る樹木や植栽
施設などの植栽を設計するときも同じことですが、図面の基本は平面図ですね。これらのメリットはもちろん全体図を把握できること、誰でも完全に理解できる説得感のある図面に仕上がることが挙げられます。造園などの場合には50分の1スケールの平面図に仕上げることが多いです。あまり細かすぎても見にくいですし、大きすぎると入り切りません。樹木を配置したら、それが高木なのか低木なのか、平面図の位置に種類などを書き記します。
立面図で見る樹木や植栽
立面図が平面図と異なるのは、地表からの高さ、壁からの距離、高木や低木と屋根との関係などが立面図により一目でわかるようになっているところでしょう。建物や地面、空、人物も書き込むと、よりリアルでわかりやすい立面図に仕上がります。
シルエットやイラストで見る樹木や植栽
樹木は大別すると、常緑樹と落葉樹に分かれます。常緑樹は温かい地方の樹木、落葉樹は寒い地方の樹木、と考えることができます。シルエットやイラストのCadデータを使用するときは、その土地に合ったものなのか、おかしなところはないか、精査しなければいけませんね。高木や低木のシルエットやイラストも、無料でダウンロードできるフリー素材(autocad(dwg)、dxf、jwcad(jww))があります。
樹木や植栽が越冬のために得た力、常緑樹が落葉樹に変化する
キンモクセイは常緑樹ですが、寒い地方へ行くと落葉樹に変化します。もっと寒く雪が降り積もるような地域では、雪布団で温かく過ごせるため、あえて落葉しない樹木も存在します。
細胞を凍らさない常緑針葉樹が寒さに強い理由
冬でも細い葉を茂らせているエゾマツやトドマツを見たことがあるかと思います。なぜ冬を越せるのかというと、冬になると細胞内の糖や樹脂の濃度を一時的に高め、凍りにくい体質に自らを変化させているのです。細胞が凍らなければ、針葉樹は冬を生きたまま過ごすことができます。そして、短い夏には効率よく生育できるように、落葉しない選択をしているのです。
無料で図面を作成したいときには、フリーのcadソフトやフリー素材をダウンロードする方法がおすすめです。autocad(dwg)、dxf、jwcad(jww)が使用でき、高木や低木、イラストやシルエットもあります。
