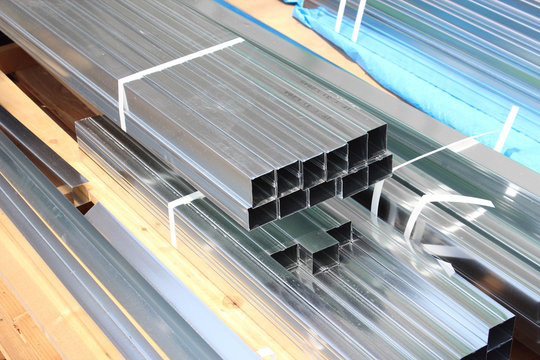鉄骨製作工場では、鉄骨製作工程の材料入荷から製品出荷まで、製作管理と品質管理を行う技術者(技術管理者)が必要で、その技術者が鉄骨製作管理技術者で、その資格を取るための試験が鉄骨製作管理技術者試験です。鉄骨製作管理技術者には1級と2級があり、それぞれ鉄骨製作管理技術者試験によって判定されます。鉄骨製作管理技術者試験の受験資格は、学歴に応じた実務経験年数によって、受験できる資格を得ることができます。
鉄骨製作管理技術者試験の過去問と解説
① 鉄骨工事の各工程の基準
鉄骨工事に関して、最も不適当なものを選べ。
1.トルシア形高力ボルトの締付けの確認では、ナット回転量に著しいばらつきがあるボルト群には、その群の全てのボルトのナット回転量を測定して平均回転角度を算出し、平均回転角度±30度の範囲のものを合格とした。
→ 適当。
トルシア形高力ボルトの締付けでは、ナット回転量のばらつきを抑えるため、平均回転角度を基準に合否判定を行う方法が適用される。
2.高力ボルト接合では、接合部に生じた肌すきが2mmで、フィラープレートを挿入しなかった。
→ 不適当。
高力ボルト接合において、接合部の肌すきが1mmを超える場合は、フィラープレートを挿入する必要があるため、本記述は誤り。
3.完全溶込み溶接とする板厚の異なる突合せ継手では、部材の板厚差による段違いが薄いほうの板厚の1/4以下、かつ10mm以下だったので、薄い部材から厚い部材へ溶接表面が滑らかに移行するよう溶接した。
→ 適当。
板厚差による段違いは、設計基準に基づき1/4以下かつ10mm以下に抑え、適切な溶接処理を行うことが求められる。
4.溶接作業では、作業場所の気温が0℃であったので、溶接線の両側約100mmの範囲の母材部分を加熱して溶接した。
→ 適当。
低温環境下での溶接では、母材の割れを防ぐため、適切な予熱処理を行う必要がある。
正解 : 2
コメント :
選択肢2の「接合部に生じた肌すきが2mmでフィラープレートを挿入しなかった」が不適当とされています。高力ボルト接合において、1mmを超える肌すきがある場合は、フィラープレートの挿入が必要とされており、本記述は基準に適合していません。
一方、選択肢1のトルシア形高力ボルトの締付け確認、選択肢3の板厚の異なる突合せ継手の処理、選択肢4の低温時の溶接作業における予熱処理はいずれも適切な手順に沿ったものであり、正しい内容です。
鉄骨工事では、接合部の精度と強度を確保するための基準が厳格に定められており、特に高力ボルト接合や溶接作業に関する基準を正確に理解し、適用することが求められます。
ワンポイント解説 :
鉄骨製作管理技術者試験では、鉄骨工事の各工程に関する基準を正しく理解することが求められます。特に高力ボルト接合に関する規定は、安全性を確保する上で重要な要素です。
高力ボルト接合では、接合部に肌すき(接合面の隙間)が生じる場合があります。日本建築学会の基準では、肌すきが1mmを超える場合は、フィラープレートを挿入する必要があります。これは、ボルトの適正な締付けと接合部の強度を確保するための措置です。しかし、本問の選択肢では、肌すきが2mmにもかかわらずフィラープレートを使用しなかったため、不適当とされています。
一方、トルシア形高力ボルトの締付け確認、異なる板厚の突合せ継手の処理、低温環境での溶接作業の予熱処理に関する記述は、いずれも鉄骨工事の基準に適合しており、適切な対応といえます。
鉄骨製作管理技術者として、鉄骨工事の品質管理を適切に行うためには、高力ボルト接合や溶接に関する基準を正しく理解し、現場での適用に注意を払うことが重要です。鉄骨製作管理技術者試験でも、これらの基準を正確に把握し、適切な判断を下せる知識が求められます。
② 溶接の品質管理
鉄骨工事における溶接に関して、最も不適当なものを選べ。
1.オーバーラップについては、削り過ぎないように注意しながら、グラインダー仕上げを行った。
→ 適当。
オーバーラップ(溶接金属が母材上にはみ出す現象)は、強度や品質に悪影響を与えるため、適切にグラインダーで仕上げる必要がある。ただし、削り過ぎると母材の強度が低下するため、慎重な処理が求められる。
2.完全溶込み溶接部の内部欠陥の検査については、浸透探傷試験により行った。
→ 不適当。
完全溶込み溶接部の内部欠陥の検査には、超音波探傷試験(UT)が用いられる。浸透探傷試験(PT)は表面欠陥の検査に適した方法であり、内部欠陥の検査には適さない。そのため、この選択肢は誤りである。
3.母材の溶接面について付着物の確認を行ったところ、固着したミルスケールがあり、溶接に支障となるため除去した。
→ 適当。
ミルスケール(酸化被膜)は溶接欠陥の原因となるため、溶接前に確実に除去することが必要である。本選択肢では、溶接前にミルスケールを除去しており、適切な対応といえる。
4.高力ボルトと溶接の併用継手については、高力ボルトを締め付けた後に、溶接を行った。
→ 適当。
高力ボルトと溶接を併用する継手では、まず高力ボルトを締め付けた後に溶接を行うのが適切な施工手順である。これは、ボルト締結後に溶接することで、適切な締結力を確保できるためである。
正解 : 2
コメント :
選択肢2の「完全溶込み溶接部の内部欠陥を浸透探傷試験で検査する」が不適当とされている。完全溶込み溶接の内部欠陥の検査には、超音波探傷試験(UT)を使用するのが正しい方法である。浸透探傷試験(PT)は表面の欠陥を検査する手法であり、内部欠陥の確認には適用できない。
一方、選択肢1の「オーバーラップのグラインダー仕上げ」、選択肢3の「ミルスケールの除去」、選択肢4の「高力ボルト締付け後の溶接」は、いずれも施工基準に沿った正しい方法であるため適当である。
鉄骨工事における溶接管理では、適切な施工方法や検査手順を理解し、適用することが求められる。鉄骨製作管理技術者試験では、溶接の基本的な管理方法や不具合防止のための基準を正確に把握することが重要である。
ワンポイント解説 :
鉄骨製作管理技術者試験では、溶接の品質管理に関する知識が問われます。特に、溶接部の欠陥検査は、鉄骨工事において安全性を確保する上で重要な要素の一つです。
完全溶込み溶接部の内部欠陥の検査には、超音波探傷試験(UT)が適用されます。超音波探傷試験は、溶接内部の欠陥を非破壊で検出することが可能なため、信頼性の高い検査方法とされています。一方、浸透探傷試験(PT)は表面の欠陥を検出するための手法であり、内部欠陥の検査には適用できません。そのため、本問では、内部欠陥の検査に浸透探傷試験を用いた記述が不適当とされています。
また、溶接の品質を確保するためには、溶接部の適切な処理が不可欠です。オーバーラップのグラインダー仕上げは、余分な溶接金属を除去し、滑らかな表面を確保するための適切な方法です。さらに、ミルスケール(酸化被膜)は溶接品質の低下を招く原因となるため、溶接前に確実に除去しなければなりません。
鉄骨製作管理技術者としては、溶接の基本的な検査方法や前処理の重要性を理解し、適切な管理を行うことが求められます。鉄骨製作管理技術者試験では、これらの基準に関する正確な知識が必要とされるため、溶接品質管理の適用基準を十分に把握し、実務に活かすことが重要です。
③ 鉄骨工事における品質管理の手順
鉄骨工事に関して、最も不適当なものはどれか。
1.トルシア形高力ボルトの締付け後の目視検査では、共回りや軸回りの有無を、ピンテールの破断により判定した。
→ 不適当。
トルシア形高力ボルトの締付け後の共回りの有無は、ピンテールの破断ではなく、1次締め後に付したマークのずれによって確認するのが正しい方法である。
2.アンカーボルト頭部の出の高さは、特記がなく、ねじが二重ナットの外に3山以上出ていることを確認した。
→ 適当。
アンカーボルトの出寸法は、施工基準に従い、適切な長さを確保することが求められる。特記がない場合でも、ねじ部の適正な突出長さを確保することが重要である。
3.床書き現寸は、特記がなく、特に必要がなかったので、工作図をもって省略した。
→ 適当。
現寸作業(床書き)は、必要に応じて行われるものであり、工作図が十分に正確であれば、省略することも可能である。
4.鋼材の受入れでは、鋼材の現品に規格名称や種類の区分等が表示され、材質が確実に識別できるものは、規格品証明書の原本の代わりに原品証明書により材料の確認を行った。
→ 適当。
鋼材の受入れ時に、現品に適切な表示があり、材質が識別できる場合は、原品証明書での確認が可能である。
正解 : 1
コメント :
選択肢1の「トルシア形高力ボルトの締付け後の共回りや軸回りの有無をピンテールの破断により判定した」が不適当とされています。トルシア形高力ボルトの共回りの有無を確認する正しい方法は、1次締め後に付したマークのずれを確認することです。ピンテールの破断は、最終的な締付けが完了したことを示すものですが、共回りの判定には適していません。
一方、選択肢2のアンカーボルトのねじ突出長さ、選択肢3の床書き現寸の省略条件、選択肢4の鋼材受入れ時の原品証明書の利用については、いずれも適切な対応方法であり、施工基準に沿ったものであるため、適当と判断されます。
鉄骨工事では、各種検査や確認作業の方法を正しく理解し、適用することが求められます。鉄骨製作管理技術者試験でも、トルシア形高力ボルトの締付け確認方法や施工基準に基づくチェック項目を正確に把握することが重要です。
ワンポイント解説 :
鉄骨製作管理技術者試験では、鉄骨工事における品質管理の手順を正しく理解することが求められます。特に高力ボルトの締付け確認方法は、安全性を確保する上で重要なポイントの一つです。
トルシア形高力ボルトは、ピンテールの破断によって適正な締付けが完了したことを確認できます。しかし、締付け時に共回り(ボルトとナットが一緒に回る現象)が発生すると、適正な締付けが行われていない可能性があります。そのため、共回りの有無は、1次締め時に付したマークのずれを基準に確認するのが正しい方法です。本問では、共回りの判定にピンテールの破断を用いた点が誤りとされています。
また、アンカーボルトのねじ突出長さの管理、床書き現寸の省略条件、鋼材の受入れ時の原品証明書の利用については、施工基準に沿った適切な方法です。これらの手順を理解し、実務に適用することが鉄骨製作管理技術者には求められます。
鉄骨製作管理技術者試験では、こうした施工基準や検査方法に関する知識が問われるため、日頃から基準に沿った適切な施工管理を意識することが重要です。
④ 鋼材の品質管理
鋼材は、曲げ等の加工により塑性歪みが蓄積し、また熱により変性し、材料特性は複雑である。また、鋼材は特定の条件下では脆性破壊のリスクがあるが、要因として設計段階だけでなく、不用意な仮付け溶接等施工段階に起因するものも多く、鋼材材質は品質管理上の重要ポイントと言える。材質の重要な判断基準として3つ挙げて説明せよ。
正解 :
1.靭性
鋼材の靭性とは、破壊されるまでのエネルギー吸収能力を指す。特に低温環境下では靭性が低下し、脆性破壊のリスクが高まるため、適切な材料選定と施工管理が必要である。靭性の評価には、シャルピー衝撃試験が用いられることが一般的である。
2.降伏強度と引張強度
降伏強度は材料が塑性変形を開始する応力、引張強度は材料が破断する応力を指し、いずれも設計において重要な指標である。鋼材の強度が適切でない場合、構造物の安全性に影響を及ぼすため、規格に適合しているか確認することが求められる。
3.炭素当量(Ceq)
炭素当量は、鋼材の溶接性を示す指標であり、溶接部の割れを防ぐための重要な管理要素である。炭素当量が高いと、溶接熱影響部での硬化が進み、脆性破壊のリスクが高まる。そのため、適切な材料選定と施工管理が求められる。
コメント :
鋼材の品質管理において、靭性、降伏強度と引張強度、炭素当量の3つは特に重要な判断基準となります。靭性は脆性破壊を防ぐために不可欠であり、特に低温環境下では適切な管理が必要です。また、降伏強度と引張強度は、構造物の設計安全性を確保する上で欠かせない特性であり、規格を満たしているかを確認することが求められます。さらに、炭素当量は溶接部の品質に大きく関わる要素であり、適切に管理しなければ溶接部の割れが発生するリスクが高まります。
鉄骨工事では、鋼材の特性や施工時の管理基準について深く理解し、正しく適用することが求められます。鉄骨製作管理技術者試験では、鋼材の特性を適切に管理し、安全性を確保するための知識が問われます。そのため、各判断基準の意味と適用方法を正確に把握し、実務に活かすことが重要です。
ワンポイント解説 :
鋼材は、加工や溶接による影響を受け、材料特性が変化するため、適切な品質管理が求められます。鉄骨製作管理技術者試験では、鋼材の品質を評価するための基準として、靭性、降伏強度と引張強度、炭素当量の3つが重要視されます。
靭性は、鋼材が破壊されるまでのエネルギー吸収能力を示し、脆性破壊を防ぐために不可欠な特性です。特に低温環境下では靭性が低下し、鋼材のもろさが増すため、適切な材質を選定することが求められます。降伏強度と引張強度は、構造物の設計安全性を確保するための基本的な指標であり、規格に適合しているかを確認する必要があります。炭素当量は、溶接性を評価するための指標であり、適切な管理が行われなければ、溶接部の割れが発生するリスクが高まります。
鉄骨製作管理技術者としては、これらの基準を理解し、鋼材の特性を適切に管理することが求められます。鉄骨製作管理技術者試験では、鋼材の品質に関する知識が問われるため、基準を正しく理解し、実務に活かすことが重要です。
⑤ 鉄骨工事の工作(曲げ加工)
鋼材等及び溶接部の許容応力度並びに材料強度を定める告示で、加工後の機械的性質、化学成分その他が加工前の品質と同等以上であることを確かめる必要があるが、次に該当する場合はこの限りではない。該当する場合、3つ答えよ。
正解 :
1.切断、溶接、局部的な加熱、鉄筋の曲げ加工その他構造耐力上支障がない加工
2.500℃以下の加熱
3.外側曲げ半径が板厚の10倍以上での曲げ加工
コメント :
鉄骨工事において、鋼材の加工後の機械的性質や化学成分が加工前の品質と同等であることを確認することは、品質管理上重要です。しかし、一定の条件を満たす場合は、この確認が省略できるとされています。
1つ目の「切断、溶接、局部的な加熱、鉄筋の曲げ加工その他構造耐力上支障がない加工」は、基本的な加工方法であり、適切に実施すれば鋼材の品質に大きな影響を与えないため、追加の品質確認は不要とされています。
2つ目の「500℃以下の加熱」は、鋼材の機械的性質に著しい影響を及ぼさない範囲の加熱処理とされ、品質確認を省略することが可能です。
3つ目の「外側曲げ半径が板厚の10倍以上での曲げ加工」は、鋼材に過度な応力を加えることなく加工できるため、追加の品質確認は不要とされています。
鉄骨製作管理技術者試験では、これらの基準を正しく理解し、適切な施工管理を行うことが求められます。鋼材の加工条件を正しく把握し、品質を維持しながら施工を進めることが、安全な鉄骨工事の実現につながります。
ワンポイント解説 :
鉄骨工事では、鋼材の加工後に機械的性質や化学成分が変化する可能性があるため、品質管理が重要になります。しかし、特定の条件を満たす場合には、この品質確認を省略することが認められています。
具体的には、①切断、溶接、局部的な加熱、鉄筋の曲げ加工など、構造耐力に支障を与えない加工、②500℃以下の加熱、③外側曲げ半径が板厚の10倍以上での曲げ加工の3つの条件が該当します。これらの条件では、鋼材の機械的性質や化学成分に大きな影響を与えないと考えられるため、追加の品質確認が不要とされています。
鉄骨製作管理技術者としては、これらの基準を理解し、鋼材の加工による品質変化を適切に管理することが求められます。鉄骨製作管理技術者試験では、これらの基準を正確に把握し、適切な施工管理を行うための知識が求められます。
⑥ 製品検査(寸法許容差)
製品検査(寸法許容差)で、管理許容差と限界許容差の違いについて、具体的な数字を上げて説明しなさい。
正解 :
管理許容差:一般的に、製品の品質を安定させるために設定される許容範囲であり、例えば、H形鋼のフランジ幅の管理許容差が±2mmである場合、この範囲内であれば通常の品質管理内で許容される。
限界許容差:設計上、安全性や機能を確保するために設定される最大許容範囲であり、例えば、H形鋼のフランジ幅の限界許容差が±4mmである場合、これを超えた場合は不適合品と判断される。
コメント :
製品検査において、管理許容差と限界許容差は、品質管理と設計上の基準を明確にするための重要な概念です。管理許容差は、日常の生産管理において品質を一定に保つための基準であり、実際の製造工程でのばらつきを考慮して設定されます。一方、限界許容差は、製品が設計上の要求を満たしているかを判断する最終的な基準であり、この範囲を超えた場合、製品は使用不可となる可能性があります。
例えば、H形鋼のフランジ幅において、管理許容差が±2mm、限界許容差が±4mmと定められている場合、±2mm以内の寸法誤差は問題ありませんが、±4mmを超える場合は不適合品となります。このように、管理許容差は工程管理の指標となり、限界許容差は製品の適合・不適合を判断する基準となります。鉄骨製作管理技術者試験では、これらの基準を理解し、適切な品質管理を行うことが求められます。
ワンポイント解説 :
鉄骨工事の製品検査では、寸法許容差の管理が重要であり、その基準として管理許容差と限界許容差が設けられています。管理許容差は、製造過程での品質管理を目的とした範囲であり、例えばH形鋼のフランジ幅において±2mmと設定されることがあります。一方、限界許容差は、製品の適合・不適合を判定する最終基準であり、例えば±4mmと設定されることがあります。
管理許容差を超えた場合でも、限界許容差以内であれば修正や特別検査の対象となることがありますが、限界許容差を超えた場合は不適合品と判断され、使用が認められません。鉄骨製作管理技術者としては、これらの許容差を理解し、適切な品質管理を行うことが求められます。鉄骨製作管理技術者試験では、これらの基準を正しく把握し、品質管理に適用できる知識が問われます。
⑦ 社内検査と受入検査
製品検査で、社内検査と受入検査で食い違いがあった場合、どのように対処するか、対処方法について説明しなさい。
正解 :
1.食い違いの内容を確認し、どの検査項目に相違があるのかを明確にする。
2.社内検査と受入検査の測定方法や使用した測定機器を照合し、測定条件の違いを確認する。
3.基準に従い、必要に応じて再測定を実施し、測定誤差や検査手順の問題がないかを検証する。
4.再測定後も食い違いが解消されない場合は、第三者検査機関などの公的機関に測定を依頼し、客観的な検証を行う。
5.最終的な判定を基に、必要に応じて製品の補修や交換を実施し、品質の確保を図る。
コメント :
社内検査と受入検査で測定結果に食い違いが生じた場合、まずその原因を明確にすることが重要です。測定方法の違いや測定機器の精度、環境条件の影響などが考えられるため、それらを照合し、適切な対処を行う必要があります。
再測定を実施することで、測定誤差が原因である場合は解決できますが、それでも食い違いが解消されない場合には、第三者機関の検査を利用し、客観的な検証を行うことが適切です。また、検査結果に基づき、必要に応じて製品の補修や交換を行うことで、最終的な品質を確保することが求められます。
鉄骨製作管理技術者試験では、品質管理の一環として、検査結果の適正な判断と対処方法についての知識が求められます。適切な対応を行い、品質トラブルを最小限に抑えることが、鉄骨製作管理技術者としての重要な役割となります。
ワンポイント解説 :
鉄骨工事における製品検査では、社内検査と受入検査で食い違いが生じることがあります。その場合、まず食い違いの内容を特定し、測定方法や測定機器の違いを照合することが重要です。
再測定を行い、測定誤差や検査環境の違いを検証した上で、問題が解消されない場合は、第三者機関による測定を依頼することが適切です。最終的な検査結果を基に、必要に応じて補修や交換を実施し、品質を確保することが求められます。
鉄骨製作管理技術者としては、検査の精度と信頼性を確保するために、測定方法の標準化や記録の管理を徹底し、食い違いが発生した際には迅速かつ適切に対応することが求められます。鉄骨製作管理技術者試験では、これらの知識を正しく理解し、品質管理の実務に活かせることが重要です。
⑧ 高力ボルト接合の種類と適用条件
JIS規格ターンバックルの高力ボルト接合で、ターンバックルの場合の取付け高力ボルトは、摩擦面の処理は必要か、不要か、理由も含めて説明しなさい。
正解 :
摩擦面の処理は不要である。
理由 :
ターンバックルの取付け高力ボルトは、摩擦接合ではなく支圧接合として機能するため、摩擦面の処理を行う必要がない。高力ボルト接合には「摩擦接合」と「支圧接合」の2種類があり、摩擦接合では摩擦力によって荷重を伝達するため摩擦面の処理が必須だが、支圧接合ではボルトと穴の支圧力、およびせん断力によって荷重を伝達するため、摩擦面処理を施さなくても強度を確保できる。
ターンバックルは調整用の部材であり、軸力を直接受けるわけではなく、締結後にボルトが抜け落ちないよう固定する役割を持つため、摩擦面処理による滑り耐力の確保は不要。JIS規格においても、支圧接合が適用される場合は、摩擦面処理の要件が除外されると規定されている。
また、摩擦面処理はショットブラスト処理や酸洗いなどの工程を伴うため、不要な場合にこれを行うことは施工の手間やコストの増加につながる。そのため、ターンバックルにおける取付け高力ボルトには、摩擦面の処理を施さずとも設計上の要求を満たすことができる。
コメント :
JIS規格に基づく高力ボルト接合では、通常、摩擦面の処理が必要ですが、ターンバックルの取付け高力ボルトは支圧接合として設計されているため、摩擦面処理は不要です。支圧接合では、ボルトと穴の支圧力およびせん断力によって荷重が伝達されるため、摩擦接合のように摩擦面処理を施す必要がありません。
ターンバックルは、ボルトの軸力を直接伝達するものではなく、調整機能を持つ部材であるため、摩擦力による滑り耐力の確保が求められない点も、摩擦面処理が不要とされる理由です。鉄骨製作管理技術者試験では、高力ボルト接合に関する基本知識だけでなく、各部材ごとの接合方法の違いを理解し、適切に施工管理できる能力が求められます。
ワンポイント解説 :
鉄骨製作管理技術者試験では、高力ボルト接合の種類と適用条件を正しく理解することが求められます。一般的に高力ボルト接合は「摩擦接合」と「支圧接合」に分類され、摩擦接合では滑り耐力を確保するために摩擦面の処理が必要ですが、支圧接合では不要とされています。
ターンバックルの取付け高力ボルトは支圧接合として機能し、ボルトと穴の支圧力によって荷重を伝達するため、摩擦面処理は必要ありません。また、ターンバックルは調整用の部材であり、摩擦力による荷重伝達を前提としていないため、摩擦面処理を施す必要がないことも理解しておくべきポイントです。
鉄骨製作管理技術者としては、接合方法の適用条件を適切に判断し、施工管理を行うことが求められます。鉄骨製作管理技術者試験では、摩擦接合と支圧接合の違いを理解し、実務に活かせる知識を身につけることが重要です。
⑨ タイトフレームの溶接強度
現場溶接で、さび止め塗装の上から行なうタイトフレームの溶接は、溶接強度に問題あるかどうか。もしあるなら、どのような問題になるか。説明しなさい。
正解 :
さび止め塗装の上からタイトフレームの溶接を行うと、溶接強度に問題がある。
理由 :
さび止め塗装の上から直接溶接を行うと、以下のような問題が生じる可能性がある。
1.溶接欠陥の発生
塗膜が溶接部で燃焼し、不純物が発生することで、ピット(くぼみ)、ブローホール(気孔)、スラグ巻き込みなどの溶接欠陥が生じる恐れがある。これにより、溶接部の強度が低下する。
2.溶接部の脆弱化
塗膜が完全に除去されずに残ると、溶接金属と母材の溶融が不十分になり、十分な接合強度が得られなくなる。特に高負荷がかかる箇所では、割れやはく離が発生しやすくなる。
3.ガスの発生による影響
塗料に含まれる有機成分が溶接熱で分解されると、気体が発生し、溶接金属内部にブローホールを生じさせる可能性がある。これは、溶接部の靭性低下や疲労強度の低下につながる。
コメント :
現場溶接において、さび止め塗装の上からタイトフレームの溶接を行うと、溶接部の品質低下を引き起こす可能性があります。特に、塗膜の燃焼によるガス発生や不純物の混入は、溶接強度の低下につながるため、施工前に塗装を完全に除去することが推奨されます。
また、溶接可能なプライマーを使用することで、一定の防錆効果を確保しつつ、溶接品質を維持することが可能です。鉄骨製作管理技術者試験では、このような溶接部の品質管理や適切な施工方法に関する知識が求められます。そのため、適切な溶接前処理の方法を理解し、実務に活かすことが重要です。
ワンポイント解説 :
鉄骨工事における現場溶接では、母材表面の状態が溶接品質に大きな影響を与えるため、溶接部の適切な前処理が求められます。さび止め塗装の上から直接溶接を行うと、塗膜の燃焼による不純物の混入やガス発生により、溶接強度の低下や欠陥が発生する可能性があります。
そのため、溶接前には塗装を完全に除去し、適切な素地処理を行うことが必要です。また、溶接後の防錆対策として、再塗装を行うことも重要になります。溶接可能なプライマーを使用することで、防錆と溶接性を両立させることができます。
鉄骨製作管理技術者としては、溶接品質の確保と防錆処理の適切なバランスを理解し、施工管理を行うことが求められます。鉄骨製作管理技術者試験では、これらの基本的な施工基準を正しく把握し、実務に適用できる知識が必要です。
⑩ 耐火被覆の施工
下塗り塗装(JIS K 5674)されている部材に半湿式の耐火被覆を施工する場合、付着性能に対する問題に、どのようなものがあるか、例を挙げて説明しなさい。
正解 :
下塗り塗装(JIS K 5674)されている部材に半湿式の耐火被覆を施工する場合、付着性能に関する問題が発生する可能性がある。具体的には以下のような問題が考えられる。
1.塗膜の剥離
JIS K 5674の下塗り塗装は、防錆性能を目的としているが、耐火被覆材との付着性が必ずしも十分ではない。特に、塗装面に油分や異物が残っている場合、耐火被覆が剥離する可能性がある。
2.耐火被覆の密着不良
半湿式の耐火被覆は、基材との機械的な付着を前提としているが、塗装面が平滑すぎると、付着力が低下することがある。その結果、乾燥後に耐火被覆が浮き上がり、施工不良となる可能性がある。
3.水分の影響による膨れ
下塗り塗装の種類によっては、耐火被覆に含まれる水分を吸収しにくく、施工後に水分が内部に残り、乾燥時に膨れや剥離を引き起こすことがある。特に、高湿度環境では問題が顕著になる。
コメント :
JIS K 5674に基づく下塗り塗装は防錆効果を目的としたものであり、耐火被覆との相性が必ずしも良いとは限りません。半湿式の耐火被覆は、施工後に基材との付着性が重要となるため、塗装面の状態によっては剥離や密着不良が発生する可能性があります。
特に、塗装面の清掃が不十分であったり、塗膜が厚すぎたりすると、耐火被覆の付着性能が低下し、施工後の品質に悪影響を及ぼします。そのため、施工前に付着試験を行い、下地処理を適切に行うことが重要です。鉄骨製作管理技術者試験では、耐火被覆の施工に関する基準や適用条件を正しく理解し、適切な施工管理ができることが求められます。
ワンポイント解説 :
鉄骨製作管理技術者試験では、耐火被覆の施工に関する知識も求められます。特に、JIS K 5674に基づく下塗り塗装が施された部材に半湿式の耐火被覆を施工する場合、付着性の問題が生じる可能性があります。
塗膜が滑らかすぎると耐火被覆の密着が不十分になり、剥離や浮き上がりが発生することがあります。また、塗装面に付着した油分や異物が耐火被覆の接着を阻害するため、施工前の下地処理が重要です。施工環境の湿度や温度も影響を与えるため、事前に付着試験を行い、適切な施工方法を選択する必要があります。
鉄骨製作管理技術者としては、耐火被覆の施工品質を確保するために、塗装面の処理方法や適切な下地処理の知識を持ち、施工計画を適切に管理することが求められます。鉄骨製作管理技術者試験では、こうした基準を正しく理解し、実務に活かせることが重要です。
鉄骨製作管理技術者試験の過去問と重要項目
鉄骨工事の溶接
鉄骨工事の溶接に関する詳細は以下の通りです。
・すみ肉溶接の端部は、応力集中を避けるため、急な止め方をせず、滑らかに回しながら溶接を行います。この処理により、強度を向上させ、溶接欠陥の発生を防ぎます。
・溶接に裏当て金を使用する場合、裏当て金の板厚を9mmとすることで、適切な溶け込みを確保し、強度を向上させます。
・組立溶接は、本溶接と同等の品質を確保することが求められます。そのため、組立段階で適切な溶接方法を選定し、歪みの発生を抑えながら精度を高めることが重要です。
・高力ボルト接合では、接合部の摩擦面をショットブラスト処理することにより、安定した摩擦係数を確保します。すべり係数0.45以上の確認試験を行わないのは、標準的な施工条件の下でこの値が確保できるためです。
・錆止め塗装において、工事現場で溶接を行う両側100mmの範囲と、超音波探傷試験の影響を受ける部分は、工場での塗装を省略します。これは、溶接や検査の品質を確保するための措置です。
・鉄骨製作工場での貫通孔加工では、設備配管用の貫通孔径が80mmであったため、孔あけ用アタッチメントを備えた手動ガス切断機を使用しました。これにより、円形の貫通孔を確保し、設計どおりの仕上がりを実現します。
・スタッド溶接の品質確認のため、異なるスタッド径ごとに、午前と午後の作業開始前に2本の試験溶接を行い、曲げ角度30度で打撃曲げ試験を実施します。これは、適切な溶接条件を設定し、品質を確保するための重要な手順です。
・トルシア形高力ボルトの締付け確認では、ナット回転量に著しいばらつきがある場合、そのボルト群全てのナット回転量を測定し、平均回転角度を算出します。そして、平均回転角度±30度の範囲内であれば合格とします。これにより、適正な締付け精度を確保します。
・完全溶込み溶接の突合せ継手では、余盛り高さが1mmであれば許容差の範囲内と判断されます。余盛り高さの管理は、溶接部の強度や加工性を考慮して行われます。
・板厚25mm以上のSN400材の組立溶接は、被覆アーク溶接を用い、低水素系溶接棒を使用します。低水素系溶接棒を使用することで、水素脆化による溶接割れを防止します。
・組立溶接時のビード配置では、溶接部に割れが発生しないように、十分な長さと4mm以上の脚長を持つビードを適切な間隔で配置します。これにより、溶接強度を確保し、歪みの影響を最小限に抑えます。
・溶接部の表面割れが発生した場合は、割れの範囲を確認し、その両端から50mm程度除去した後、船底型形状に仕上げて補修溶接を行います。適切な補修溶接を施すことで、溶接部の強度を維持します。
・溶接金属中の水素量が多いと、割れが発生しやすいため、使用する溶接材料の管理が重要です。特に、低水素系の溶接材料を使用することで、水素脆化を防ぐことができます。
・溶接ひずみは、溶接時の温度が高いほど発生しやすくなるため、適切な溶接順序や歪み取り技術を駆使することが求められます。
・過大な余盛りは、グラインダーなどで適正な高さに削り取ることで、溶接部の応力集中を防ぎます。余盛りの管理は、溶接部の品質を向上させる重要な要素です。
・スタッド溶接は、アークスタッド溶接の直接溶接により、下向き姿勢で行います。これにより、溶接部の溶け込みが確実になり、強度が確保されます。
ワンポイント解説 :
鉄骨製作管理技術者試験では、溶接に関する基礎知識と実務に即した管理手法が問われます。特に、すみ肉溶接や完全溶込み溶接の処理方法、スタッド溶接の試験方法、高力ボルトの締付け管理などは、実務でも重要なポイントとなります。
また、溶接部の品質を維持するためには、溶接金属中の水素管理や適切な溶接順序、歪み対策が不可欠です。溶接時の温度管理も重要であり、温度が高すぎると溶接ひずみが発生しやすくなるため、適正な施工管理が求められます。
溶接後の補修方法についても、試験で問われることがあります。溶接部の割れや過大な余盛りは、適切な補修を行うことで強度を確保できます。鉄骨製作管理技術者試験では、溶接の基礎知識に加え、現場での実践的な判断力が求められるため、各項目をしっかりと理解し、適用できるようにすることが重要です。
鉄骨の加工組立
鉄骨の加工組立に関する詳細は以下の通りです。
・熱間曲げ加工は、200〜400℃の青熱脆性域では行ってはなりません。この温度域では鋼材の靭性が低下し、割れや変形が発生しやすくなるため、適切な温度管理が必要です。
・高力ボルト用の孔開け加工は、製作工場でのドリル開けを原則とします。ドリル開けは、ボルト孔の精度を確保し、施工後の締結力を安定させるために重要な工程です。
・部材を接合する際には、正確な位置決めを行い、適切な固定を行う必要があります。そのため、治具を使用し、部材を拘束することで精度の高い組立を実現します。
・鉄骨製作工場と工事現場で異なる基準巻尺を使用する場合は、製作開始前に照合を行い、測定誤差を防ぐことが重要です。巻尺の誤差が施工精度に影響を与えないよう、適切な管理が求められます。
・柱梁接合部のエンドタブは、裏当て金に溶接することで、溶接の始点および終点の品質を確保し、応力集中を防ぎます。
・高力ボルト接合に使用するスプライスプレートは、ガス切断で加工します。ガス切断は、精度が求められる加工方法であり、適切な処理を行うことで、設計どおりの寸法を確保できます。
・鋼板の曲げ加工を常温で行う場合、内側曲げ半径 Rは、板厚 tの2倍以上を確保して加工します。これにより、鋼材の塑性変形を適切に制御し、曲げ加工による割れや強度低下を防ぐことができます。
・400N/mm²級鋼のひずみ矯正を局部加熱で行い、加熱後に空冷する場合、加熱温度は850〜900℃の範囲とします。適切な加熱温度を確保することで、鋼材の機械的性質を損なうことなく、歪みを除去できます。
・鋼板の切断は、NCガス切断機で行います。NCガス切断機は、高精度な切断が可能であり、大量の部材を均一な品質で加工するために適した方法です。
・柱梁接合部のエンドタブの取付けは、裏当て金に組立溶接として行います。これにより、溶接品質の均一性を確保し、強度を向上させることができます。
・溶融鉛めっきした高力ボルトの孔径は、同じ呼び径の高力ボルトの孔径と同じ径とします。これは、施工時の適切な締結力を確保し、設計どおりの接合強度を得るための基準です。
・柱の十字形鉄骨に設ける梁主筋の貫通孔は、耐力低下の大きいフランジを避け、ウェブに設けます。ウェブに貫通孔を設置することで、構造の強度を維持しつつ、必要な配管や配線の通過を確保します。
ワンポイント解説 :
鉄骨製作管理技術者試験では、鉄骨の加工や組立に関する基礎知識が問われます。特に、熱間曲げ加工の適切な温度管理や高力ボルト用の孔開け加工方法、鋼材のひずみ矯正の手順などは、実務に直結する重要な知識となります。
また、柱梁接合部のエンドタブの取付け方法や、スプライスプレートの加工方法など、溶接とボルト接合に関する基準を理解しておくことが求められます。さらに、鋼板の切断や貫通孔の設置に関しては、精度の高い加工を行うことが、鉄骨構造の品質向上につながります。
鉄骨製作管理技術者としては、これらの加工基準を正しく理解し、施工管理に適用することが必要です。鉄骨製作管理技術者試験では、各工程の適切な管理方法を習得し、現場での品質確保に活かせるようにすることが重要です。
鉄骨の建て入れ直し
鉄骨の建て入れ直しに関する詳細は以下の通りです。
・建て入れ直しは、本接合を行う前の段階で実施します。これは、鉄骨の垂直精度や位置を適切に調整し、構造の安定性を確保するための重要な工程です。
・高力ボルト接合の場合、建て入れ直しが完了したら、速やかに本締めを行います。これにより、建て方の誤差が固定され、構造全体の精度が向上します。
・建て入れ直しにワイヤロープを使用する場合は、引きと返しをたすき掛けに張ることで、均等な力がかかり、安定した調整が可能となります。
・ターンバックル付き筋かいがある鉄骨構造物では、筋かいを使って建て入れ直しを行ってはなりません。筋かいは構造体の安定化に寄与する部材であり、無理な調整を行うと構造に悪影響を及ぼす可能性があります。
ワンポイント解説 :
鉄骨製作管理技術者試験では、建て入れ直しの適切な方法が問われます。建て入れ直しは、本接合前に行うことで施工精度を高め、構造の安定性を確保する重要な工程です。特に高力ボルト接合では、建て入れ直し後に速やかに本締めを行うことで、位置ずれを防ぎます。
ワイヤロープをたすき掛けにすることで、均等な力をかけながら安定した調整が可能となります。一方で、ターンバックル付き筋かいを使用すると、構造の強度低下を招くため、適切な方法で施工することが重要です。鉄骨製作管理技術者としては、各部材の役割を理解し、安全かつ精度の高い施工を管理することが求められます。
高力ボルトの摩擦接合
高力ボルトの摩擦接合に関する詳細は以下の通りです。
・ボルトの孔径は、ボルトの公称軸径に2.0mmを加えた径とします。これは、高力ボルトが適切に挿入され、施工精度を確保するための基準です。
・摩擦面の錆の発生状態は、鋼材の表面が一様に赤く見える程度とし、過度な腐食や汚れがない状態を維持します。適度な錆は摩擦係数を向上させるため、完全に除去する必要はありません。
・一次締め後は、ボルト軸、ナット、座金、鋼材面にマーキングを行い、本締めを実施します。このマーキングにより、締め付け作業の確実性を確認し、ボルトの緩みを防ぐことができます。
・ナットとボルト、またはナットと座金が供回りを生じた場合は、適切な締結力を確保するために、新しいセットに交換します。摩耗や変形が生じた部材をそのまま使用すると、締結強度が低下する可能性があるためです。
ワンポイント解説 :
鉄骨製作管理技術者試験では、高力ボルトの摩擦接合に関する知識が求められます。特に、ボルトの孔径の設定、摩擦面の適切な状態、正しい締め付け手順を理解することが重要です。ボルト孔径は公称軸径に2.0mm加えた値とし、摩擦面の錆は適度な状態を維持することで、適切な摩擦力を確保します。
また、一次締め後のマーキングは、締め付け作業の確認と品質管理のために不可欠です。ナットやボルトが供回りした場合には、必ず新しいセットに交換し、適正な締結力を維持することが求められます。鉄骨製作管理技術者としては、これらの施工基準を正しく理解し、確実な品質管理を行うことが重要です。
鉄骨の錆止め塗装
鉄骨の錆止め塗装に関する詳細は以下の通りです。
・素地調整では、鋼材表面に適切な粗さを与えることで、塗膜の付着性を向上させます。これにより、塗装が剥がれにくくなり、防錆効果を長期間維持できます。
・塗膜にふくれや割れが発生した場合は、その部分の塗膜を完全に剥がし、素地を適切に調整した後、再塗装を行います。これにより、塗膜の均一性を保ち、品質を確保できます。
・錆止め塗装後に塗り残しを発見した場合は、そのまま上塗りせず、再度素地調整を行い、適切に再塗装を実施します。下地の状態を整えることで、塗装の密着性が向上し、耐久性を確保できます。
・工事現場で溶接を行う際、錆止め塗装をしない部位として、耐火被覆接着面や組み立て時に肌合わせとなる部分があります。これらの部位は直接溶接や接着が必要なため、塗膜が施工の妨げとならないように除去しておきます。
ワンポイント解説 :
鉄骨製作管理技術者試験では、錆止め塗装の適切な施工方法や管理基準が問われます。塗膜の密着性を高めるためには、素地調整によって鋼材表面に適切な粗さを与えることが重要です。また、塗膜のふくれや割れが発生した場合は、その部分を剥がしてから再塗装を行い、均一な仕上がりを確保する必要があります。
錆止め塗装後に塗り残しが見つかった場合、再度素地調整を行うことで、塗膜の密着性と防錆性能を維持できます。さらに、工事現場での溶接部や耐火被覆接着面には塗装を施さないことが求められるため、適切な範囲を把握し、施工管理を徹底することが重要です。
鉄骨製作工場での錆止め塗装
鉄骨製作工場での錆止め塗装に関する詳細は以下の通りです。
・ローラー支承の摺動面で削り仕上げが施された部分は、滑り性能を確保するため塗装を行いません。塗装を施すと摩擦係数が変化し、支承の機能が損なわれる可能性があるためです。
・角形鋼管柱の密閉される閉鎖形断面の内面は、塗装を行いません。密閉空間内では空気の流動がなく、錆の進行が抑えられるため、塗装による影響を最小限にするための処置です。
・コンクリートに埋め込む鉄骨梁に溶接される鋼製の貫通スリーブの内面には、適切な錆止め塗装を施します。これにより、スリーブ内に発生する錆を防ぎ、耐久性を確保します。
・柱ベースプレート下面のコンクリートに接する部分には、付着強度を確保するため塗装を行いません。塗装を施すと、コンクリートとの付着力が低下し、構造上の強度に影響を与える可能性があるためです。
ワンポイント解説 :
鉄骨製作管理技術者試験では、錆止め塗装の適用範囲を正しく理解することが求められます。塗装を行わない箇所として、摺動面や閉鎖形断面の内面、コンクリートと接する部分があります。摺動面では滑り性能を維持し、閉鎖形断面では密閉環境を考慮して塗装を省略します。
一方、コンクリートに埋め込む貫通スリーブの内面には、適切な錆止め塗装を施し、錆の発生を防ぐ必要があります。鉄骨製作管理技術者としては、各部位の特性に応じた塗装の有無を理解し、適切な施工管理を行うことが重要です。
鉄骨の検査
鉄骨の検査に関する詳細は以下の通りです。
・柱に現場継手のある階の建方精度について、特記がなかったため、階高の管理許容差を±5mmとしました。この許容差は、構造の安定性を確保するために適用される基準です。
・高力ボルト接合時に接合部の肌すきが0.5mmである場合、フィラープレートは挿入しません。フィラープレートは通常、肌すきが1.0mmを超える場合に使用され、必要以上の補填を避けることで接合強度を適切に維持します。
・鉄骨製作工場の選定において、設計図書で加工能力が国土交通大臣のRグレード以上と指定されていたため、Mグレードの鉄骨製作工場を選定しました。これは、MグレードがRグレード以上の基準を満たしているためです。
・溶接部の受入検査では、特記がない場合、目視による抜取検査を行います。溶接部の部位や種類ごとにロットを構成し、10%に相当する部材数をサンプリングし、表面欠陥や精度を確認します。
ワンポイント解説 :
鉄骨製作管理技術者試験では、鉄骨の検査基準や精度管理が重要なポイントとなります。建方精度の管理許容差は、設計指示がない場合、±5mmが一般的に適用されます。また、高力ボルト接合時の肌すきについては、1.0mmを超えない場合、フィラープレートを挿入しないのが基本です。
鉄骨製作工場の選定では、設計図書に記載されたグレード要件を満たすことが重要です。さらに、溶接部の受入検査は、特記がない場合は目視による抜取検査が行われ、ロット単位で10%の部材を検査対象とするのが一般的な手法です。鉄骨製作管理技術者としては、これらの検査基準を理解し、適切に施工管理を行うことが求められます。
鉄骨の抜取検査
鉄骨の抜取検査に関する詳細は以下の通りです。
・検査対象は、同じ条件で製作された部材をまとめたロットとして処理されます。ロット単位での検査により、効率的かつ統一的な品質管理が可能となります。
・品質判定基準や抜取検査方式は明確に定められており、あらかじめ決められた基準に基づいて検査が実施されます。これにより、客観的で一貫性のある品質評価が可能となります。
・試料は、ロット全体の代表として公平な方法で抜き取られる必要があります。特定の部材に偏ることなく無作為に選定することで、ロット全体の品質を正確に反映できます。
・合格したロット内に少量の不良品が混入することは許容される場合があります。ただし、品質管理基準を満たす範囲内であることが前提であり、大きな欠陥が認められた場合は適切な対応が求められます。
ワンポイント解説 :
鉄骨製作管理技術者試験では、抜取検査の方法や基準について正しく理解することが重要です。抜取検査は、全数検査を行うことが困難な場合に、ロット単位で行われる品質管理手法です。品質判定基準と検査方式は事前に定められており、公平な方法で試料を抽出することが求められます。
また、抜取検査では、合格ロット内に少量の不良品が含まれることが許容される場合がありますが、基準を超える欠陥が発見された場合は、追加検査や再検査が必要となります。鉄骨製作管理技術者としては、適切な検査手順を理解し、品質管理の精度を確保することが求められます。
鉄骨の品質管理
鉄骨の品質管理に関する詳細は以下の通りです。
・不適合とは、製品や工程が規定された要求事項を満たしていない状態を指します。品質基準に適合しない場合、適切な是正措置が求められます。
・かたよりとは、測定値の期待値と真の値との差を指します。測定においてかたよりが生じると、結果の信頼性が低下するため、適切な補正や測定方法の見直しが必要です。
・不確かさとは、測定結果に対して真の値が含まれる可能性のある範囲を推定することを指します。測定誤差や環境要因を考慮し、不確かさを管理することが品質保証において重要となります。
・工程管理とは、製品やサービスの特性のばらつきを抑え、品質を安定して維持するための管理活動を指します。適切な工程管理を行うことで、品質の向上と製造の効率化が実現されます。
ワンポイント解説 :
鉄骨製作管理技術者試験では、品質管理の基本概念についての理解が求められます。不適合とは、規定の基準を満たしていない状態を指し、品質保証の観点から適切な対策が必要です。また、かたよりは、測定結果と真の値の差を示し、測定精度の向上が求められます。
不確かさは、測定結果の信頼性を評価する重要な指標であり、適切な範囲を把握することが重要です。工程管理は、製品のばらつきを抑え、品質の安定を確保するための手法であり、鉄骨製作の現場においても適切な管理が求められます。鉄骨製作管理技術者としては、これらの品質管理手法を理解し、実務で適用できる知識を身につけることが必要です。
鉄骨の品質管理表の作成
鉄骨の品質管理表の作成に関する詳細は以下の通りです。
・品質管理表は、工種別や部位別に作成し、それぞれの作業に適した管理基準を設定します。これにより、各工程の品質を適切に管理し、不具合の発生を防ぎます。
・検査の時期、方法、頻度を明示することで、品質管理の一貫性を確保します。適切なタイミングで検査を実施することで、施工品質の向上と不具合の早期発見につながります。
・管理値を外れた場合の処置を事前に定めておくことが重要です。万が一、不適合が発生した際には、迅速な是正措置を講じ、品質の確保と施工遅延の防止を図ります。
・管理項目は、重要度や必須項目、測定数などに基づいて決定します。品質に直結する要素を適切に管理することで、施工基準を満たし、安全性の高い構造物を実現します。
ワンポイント解説 :
鉄骨製作管理技術者試験では、品質管理表の適切な作成方法が求められます。管理表は、工種や部位ごとに作成し、各工程の品質を維持するための基準を明確にすることが重要です。
また、検査の時期・方法・頻度を事前に設定し、品質管理の一貫性を確保する必要があります。管理値を逸脱した場合の対応をあらかじめ定めておくことで、不適合発生時にも迅速な対応が可能となります。鉄骨製作管理技術者としては、品質管理表を適切に作成し、施工管理に活かすことが求められます。
鉄骨製作管理技術者試験の科目ごとの勉強法
「鉄骨構造」の勉強法
出題内容の分析
「鉄骨構造」では、鉄骨の構造力学や設計に関する基本的な知識が問われます。特に、構造設計の基本概念や、接合部、接合方法に関する理解が必要です。出題は、鉄骨構造の理論や設計基準に基づいた内容で、実際の設計に即した問題が多く、技術的な知識と計算能力が要求されます。
試験突破の第一歩:参考書で学ぶ基礎
基礎固めには、まず鉄骨構造の基本的な理論を理解することが重要です。以下の項目を中心に学習しましょう。
・構造力学の基礎
構造力学の基礎をしっかりと理解します。鉄骨構造を設計する際に必須となる力の作用や、荷重計算について学びます。
・構造設計の概要
鉄骨構造を設計するための基準や方法について理解します。設計に必要な法令や基準も覚えておくことが大切です。
・接合部及び接合方法
鉄骨構造における接合部の重要性と、接合方法(溶接、ボルト接合)の特徴を学びます。
・鋼材の種類と特性
引張強さ520N級までの鋼材や、板厚60mm程度の鋼材の種類と特性について理解します。
試験問題集を活かした応用力養成術
基礎を理解した後は、問題集を活用して応用力を高めましょう。鉄骨構造の計算問題が多いため、以下の内容に注力して問題を解きます。
・荷重計算と力学的問題
実際の構造設計に関連する荷重計算や力の作用に関する問題を解きます。
・接合部の設計問題
接合部の設計に関する問題を解き、接合方法の適用方法を理解します。
・鋼材の特性に関する問題
鋼材の種類や特性を基にした設計に関する問題を解きます。
試験で暗記が重要なポイント一覧
鉄骨構造では、設計基準や鋼材の特性に関する知識を暗記しておくことが重要です。特に以下のポイントを押さえましょう。
・構造設計の基準
鉄骨構造を設計するための基本的な基準や法令を覚えておきます。
・鋼材の特性
引張強さや板厚など、鋼材の特性を理解し、実際の設計にどう反映するかを覚えます。
・接合方法の特徴
溶接やボルト接合の特徴や適用基準を暗記しておくと役立ちます。
試験勉強の序盤で押さえるべきポイント
最初に取り組むべきは、構造力学の基本的な概念と鉄骨設計の概要です。これにより、設計の基礎を理解し、後の詳細な問題に取り組む土台を作ります。次に、接合部や鋼材の特性に進み、さらに実践的な知識を深めましょう。
忙しい人向けの試験効率学習テクニック
時間がない場合、過去問や頻出問題を中心に学習し、特に計算問題や設計基準を効率的に覚えることが重要です。また、設計の流れや基本的な計算式を暗記し、実際の問題でどのように応用するかを理解することが効率的な学習方法となります。
「鉄骨加工」の勉強法
出題内容の分析
「鉄骨加工」では、鉄骨製作における加工技術や施工管理、工程管理に関する知識が求められます。特に、鋼材の加工、溶接技術、高力ボルト工作、防錆塗装などの技術的内容が問われます。問題は実際の鉄骨加工現場に基づいた技術や管理方法に関連しており、実務に即した知識が重要です。
初心者必見!参考書で基礎を築く方法
基礎固めの段階では、鉄骨加工に関する基本的な知識をしっかり学習することが求められます。特に以下の項目を重点的に学びましょう。
・製作計画と工程管理
製作計画を立てる方法と、施工工程を管理する方法を理解します。
・鋼材加工技術
鋼材を加工する方法や、その後の仕上げ技術を学びます。
・溶接技術
溶接方法(TIG溶接やアーク溶接など)の選定や技術を理解します。
・高力ボルト工作
高力ボルトの種類や取り付け方法、締め付け基準を学びます。
試験の実力アップ!問題集の効果的活用法
基礎を学んだ後、問題集を使って応用力を高めましょう。特に、以下の内容を重点的に解くことで、実践的な知識を深めます。
・工作図作成
図面を基に加工手順を理解する問題を解きます。
・溶接技術の問題
溶接方法を選ぶ問題や、施工中の注意点を解くことで知識を定着させます。
・工程管理問題
製作スケジュールや進捗管理についての問題を解き、工程管理の知識を実践的に学びます。
暗記が得点に直結する試験の必須事項
この科目では、特定の技術や規格を暗記しておくことが重要です。特に以下の点を押さえておきましょう。
・溶接の種類と特徴
各種溶接(TIG溶接、アーク溶接など)の特徴や適用方法を覚えます。
・高力ボルト接合
高力ボルトの種類や締め付け方法について暗記しておきます。
・加工の手順
鋼材を加工する手順や基本的な設備について理解しておきます。
勉強計画の最初に試験対策でやるべきこと
最初に取り組むべきは、鉄骨加工の基本的な手順や製作計画の立案方法です。これにより、加工工程の流れを理解し、実務に必要な知識を身につけることができます。その後、溶接技術やボルト接合に進み、より実践的な知識を深めましょう。
限られた時間で挑む試験の効率勉強法
時間がない場合、過去問を中心に学習し、特に頻出の溶接技術や高力ボルト工作に関する問題に絞って学びます。また、重要ポイントを絞って学習し、効率的に知識を深めることが大切です。
「品質管理」の勉強法
出題内容の分析
「品質管理」では、鉄骨製作における品質の保証と管理に関する基礎知識が問われます。具体的には、品質マネジメントシステム、検査方法、製作工程での品質管理などが重要なテーマです。特に、非破壊検査や溶接部の検査方法に関する理解が求められ、統計的な品質管理も出題されることが多いです。
参考書を活かして試験の基礎を攻略
まずは品質管理の基本概念を押さえることが重要です。以下のポイントをしっかり理解しましょう。
・品質マネジメントシステムの基礎
品質管理の基本となる考え方や、ISO規格などの品質マネジメントシステムについて学びます。
・統計的品質管理
品質を統計的に管理する方法(管理図、標準偏差など)について理解します。
・検査手法
製作工程における製品検査方法、特に溶接部や非破壊検査の基本的な方法を学びます。
試験対策問題集で応用力を鍛えるコツ
基礎を理解した後、問題集を使って実践的な知識を身につけます。特に以下に注力しましょう。
・統計的品質管理の問題
管理図や統計的な手法に関する問題を解き、実務に役立つ技能を身につけます。
・検査方法の問題
製品検査や溶接部検査に関する問題を解くことで、各検査の流れや方法を実践的に理解します。
暗記が重要な試験対策ポイントの一覧
品質管理においては、検査基準や統計的手法を覚えておくことが重要です。特に以下の点を押さえておきましょう。
・品質マネジメントシステム
ISO規格や品質管理システムの基準は暗記しておくと便利です。
・検査基準
溶接部や製品の検査方法、非破壊検査の技術をしっかり暗記しましょう。
試験における最初のステップを明確にする
まず最初に取り組むべきは、品質管理の全体像を理解することです。品質マネジメントシステムや統計的手法を学び、品質管理の流れをつかんでから、検査方法や品質保証の具体的な手法に進みましょう。
試験の勉強時間を最大限に活かす方法
時間がない場合は、過去問を中心に学習し、特に統計的品質管理や検査方法に絞って勉強すると効率的です。基本的な概念とよく出題されるポイントを重点的に学び、理解を深めましょう。
「安全管理」の勉強法
出題内容の分析
「安全管理」では、作業現場での安全確保に関する基本的な知識が問われます。特に、労働安全衛生法や重量物の取り扱い、輸送管理に関連する内容が重要です。試験では、労働安全の基本法令や、現場でのリスク管理に関する実務的な問題が出題されることが多いです。
参考書を活用した基礎学習のコツ
基礎固めには、安全管理の法令や現場の安全対策に関する理解を深めることが必要です。以下の項目を重点的に学習しましょう。
・労働安全衛生法の概要
労働者の安全を守るための基本法令である「労働安全衛生法」の内容を理解します。特に、事業者の責任や安全管理の義務について詳しく学びます。
・重量物の取り扱い
鉄骨製作現場における重量物の取り扱いに関する安全規則や、リスク管理の方法を学びます。
・輸送管理の基礎
鉄骨やその他の材料の輸送時の安全管理について、荷役作業や輸送中のリスク管理について理解します。
試験問題集を活かした応用力養成術
基本的な知識を学んだ後、問題集を使って実践的な問題に取り組みましょう。以下のような問題を解くことで応用力を高めます。
・安全管理に関する法令問題
労働安全衛生法に関連する問題を解き、法令の理解を深めます。
・重量物取り扱いの安全管理問題
重量物の取り扱いやリスク管理に関する問題を解き、現場での安全対策を実践的に学びます。
・輸送管理の問題
輸送管理に関する安全対策や法令を理解するための問題を解きます。
確実に暗記しておく試験の要点整理
安全管理においては、法令や安全対策を確実に覚えておくことが重要です。特に以下のポイントを押さえましょう。
・労働安全衛生法
労働安全衛生法の基本的な内容や、事業者・労働者の義務に関する部分を暗記しておくと役立ちます。
・重量物の取り扱い方法
重量物の取り扱いに関する基本的な安全対策や手順を覚えておくと良いです。
・輸送中の安全管理
輸送時の安全管理に関するポイントを覚えておきましょう。
試験対策で最初に着手するべき事項
まず最初に取り組むべきは、労働安全衛生法の基本的な内容と、その適用範囲を理解することです。これにより、安全管理の基盤を築き、その後に重量物取り扱いや輸送管理など、より具体的な安全対策に進みます。
忙しい人向けの試験効率学習テクニック
時間がない場合、過去問や頻出問題を中心に学習しましょう。特に、労働安全衛生法に関する基本的な部分を確実に押さえ、重量物や輸送管理に関連する問題も重点的に解きます。暗記するポイントを絞り、効率的に学習することが求められます。
「建築法規」の勉強法
出題内容の分析
「建築法規」では、建築基準法を中心とした法令に関する知識が問われます。鉄骨製作に関連する法令や規制が、建築物の設計や施工にどのように影響を与えるかを理解することが重要です。具体的には、建築基準法や構造に関する法規、さらには建築に関連する特別な規定についても問われます。
試験突破の第一歩:参考書で学ぶ基礎
建築法規は、法令に基づく規定を理解することが最も重要です。以下の項目に注力しましょう。
・建築基準法の概要
建築基準法は、建築物の安全性を確保するための基本的な法令です。法令の目的、内容、適用範囲などをしっかり理解します。
・構造関係法規の概要
建物の構造に関する法規(耐震基準など)について学び、鉄骨構造に関連する規定を理解します。
・建築物の施工基準
鉄骨構造を使用した建築物の施工に関する基準を理解します。施工時に守るべき規定や基準についても確認します。
問題集を攻略して実践力を磨く方法
基礎知識を身につけた後は、問題集を使って実践的な問題に取り組みましょう。以下のポイントを重点的に学びます。
・建築基準法に関する問題
建築基準法に基づいた法令や規定を理解し、実務に即した問題に解答します。
・構造関係法規の問題
建築物の構造に関連する法規や規定についての問題を解き、実際の設計や施工にどのように適用されるかを理解します。
試験で覚えておきたい重要事項のまとめ
建築法規では、特に法令の内容や基準を暗記することが必要です。以下の点をしっかり覚えておきましょう。
・建築基準法の主要な規定
建築基準法の基本的な規定や、鉄骨構造に関連する部分をしっかり覚えておくことが大切です。
・耐震基準や構造規定
建物の耐震性に関する規定や、鉄骨構造に関連する構造基準を覚えておきましょう。
初心者向け試験の取り組み方ガイド
最初に取り組むべきは、建築基準法の基本的な内容を理解することです。法令の目的や、鉄骨構造に関連する部分を学び、次に施工基準や構造関係法規に進みます。
忙しい人向けの試験効率学習テクニック
時間がない場合、特に建築基準法の基本的な規定を重点的に学び、鉄骨構造に関する規定を中心に過去問を解くことが効果的です。出題されやすいポイントを絞り、効率的に学習しましょう。また、施工基準や構造規定については、要点を押さえて学ぶことが大切です。
鉄骨製作管理技術者とは
鉄骨製作管理技術者とは、鉄骨製作工場で鉄骨製作工程の材料入荷から製品出荷、製作管理と品質管理を行う技術者(技術管理者)です。
鉄骨製作管理技術者資格の種類
鉄骨製作管理技術者には、1級と2級があります。1級技術者は、高層建築物の鉄骨の品質・性能について構造学的な判断によって、生産・品質管理ができる技術者です。2級技術者は、中・低層建築物の鉄骨の品質・性能を、規準・規格によって判定でき、生産・品質管理ができる技術者です。
資格の登録と更新手続き
鉄骨製作管理技術者の資格は、試験合格後に登録することで得られます。鉄骨製作管理技術者資格の有効期間は5年間です。有効期間満了後は、更新手続きを行うことで資格を継続できます。
1回目・2回目の更新時の手続き
1回目の更新では有効期間満了の前年5月中旬頃に郵送される更新講習と修了考査、2回目の更新では有効期間満了の前年5月中旬頃に郵送される更新講習と論文に合格する必要があります。
更新費用は、受講料16,500円(税込)と登録料5,500円(税込)の計22,000円(税込)です。
3回目以降の更新時の手続き
3回目以降の更新では、更新講習(午前の部のみ)を受講するか、更新書類審査(要鉄骨工事に係る職務経歴)に合格する必要があります。
更新費用は、書類審査料:5,500円(税込)と登録料5,500円(税込)の計11,000円(税込)です。
鉄骨製作管理技術者試験 その1
鉄骨製作工場では、鉄骨製作工程の材料入荷から製品出荷まで、製作管理と品質管理を行う技術者(技術管理者)が必要で、その技術者が鉄骨製作管理技術者で、その資格を取るための試験が鉄骨製作管理技術者試験です。鉄骨製作管理技術者試験はマークシート方式で、1級も2級も2時間で50問出題されます。鉄骨製作管理技術者の資格を得た後には、5年ごとに更新講習があり、講習後の終了考査に合格する必要があります。
鉄骨製作管理技術者試験1級の問題の内容は、鉄骨構造9問・鉄骨加工20問・品質管理15問・安全管理3問・建築法規3問のように出題され、出題される問題数は、年によって異なるようです。2級の問題も同じような出題数ですが、鉄骨構造が4問、鉄骨加工が25問と鉄骨加工に重点が置かれているようです。
受験資格
鉄骨製作管理技術者試験の受験資格は、学歴に応じた実務経験年数によって、受験できる資格を得ることができます。
鉄骨製作管理技術者試験はマークシート方式で、1級も2級も2時間で50問出題されます。試験の合格率は1級も2級も65%近くあり、高い合格率と言うべきでしょう。
この高確率の高さは、試験問題の難易度が低いということではなく、受験者は皆、鉄骨製作工場で働いて経験も豊富で、それなりの高い技術レベルにあると思われます。また、資格取得のための勉強も重ねていて、そのため合格率が高いと思われます。
・必要実務経験年数
| 1級試験 | 2級試験 | |||
| 学歴又は資格 | 指定学科 | 指定学科以外 | 指定学科 | 指定学科以外 |
| 大学・大学院 | 1年以上 | 3年以上 | 1年以上 | 2年以上 |
| 短大・高専 | 3年以上 | 5年以上 | 1年以上 | 2年以上 |
| 専修学校の専門課程 (修業年限2年以上) |
3年以上 | – | 1年以上 | – |
| 高校 | 5年以上 | 7年以上 | 2年以上 | 3年以上 |
| 鉄骨制作管理技術者2級 | 資格取得後3年以上 | – | ||
| 上記以外 | 10年以上 | 5年以上 | ||
| 備考 | 次の資格を有する者は、上記に関係なく受験可 ①一級建築士 ②技術士(建設部門) ③WES8103溶接管理技術者1級以上 |
次の資格を有する者は、上記に関係なく受験可 ①二級建築士以上 ②WES8103溶接管理技術者2級以上 |
||
試験日程・申し込み方法
鉄骨製作管理技術者試験は、毎年10月下旬頃に実施されています。申し込み受付期間は、6月上旬~7月下旬頃までです。
試験地
鉄骨製作管理技術者試験は、札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡で実施されています。
受験料金・支払い方法
鉄骨製作管理技術者試験の受験料は、13,200円(税込)です。
鉄骨製作管理技術者試験 その2
試験内容
| 1級試験 | 2級試験 | |
| 試験時間 | 2時間 | |
| 出題形式 | 択一形式(マークシート) | |
| 出題分野 | ①鉄骨構造・・・9問 ②鉄骨加工・・・20問 ③品質管理・・・15問 ④安全管理・・・3問 ⑤建築法規・・・3問 |
①鉄骨構造・・・4問 ②鉄骨加工・・・25問 ③品質管理・・・15問 ④安全管理・・・3問 ⑤建築法規・・・3問 |
鉄骨製作管理技術者試験の出題内容(1級)
鉄骨製作管理技術者試験1級の問題の内容は、鉄骨構造9問・鉄骨加工20問・品質管理15問・安全管理3問・建築法規3問のように出題され、出題される問題数は、年によって異なるようです。2級の問題も同じような出題数ですが、鉄骨構造が4問、鉄骨加工が25問と鉄骨加工に重点が置かれているようです。
| 出題範囲 | 主な内容 | 設問数 |
| 鉄骨構造 |
|
9問 |
| 鉄骨加工 |
|
20問 |
| 品質管理 |
|
15問 |
| 安全管理 |
|
3問 |
| 建築法規 |
|
3問 |
鉄骨製作管理技術者試験の出題内容(2級)
鉄骨製作管理技術者試験2級では、鉄骨加工を行う上で、設計図書を受領した後、製作計画の立案から鋼材の加工、組立て、溶接、塗装、発送及び現場における製品引き渡しまでの一貫した管理を行うために必要な専門知識・基礎知識及び対応能力についてが問われます。
| 出題範囲 | 主な内容 | 設問数 |
| 鉄骨構造 |
|
4問 |
| 鉄骨加工 |
|
25問 |
| 品質管理 |
|
15問 |
| 安全管理 |
|
3問 |
| 建築法規 |
|
3問 |
鉄骨製作管理技術者試験 その3
合格基準
・1級試験
普遍化した工法による高層建築物等の鉄骨の品質・性能等について構造学的判断ができ、生産・品質管理が一貫して行うことができる知識及び技術。
・2級試験
普遍化した工法による中・低層建築物等の鉄骨の品質・性能等について、定められた規準・規格等と照合して判定ができ、生産・品質管理が一貫して行うことができる知識及び技術。
合格率・難易度
鉄骨製作管理技術者試験の合格率は、1級も2級も65%程度です。比較的に難易度の低い試験と言うべきでしょう。ただし、試験問題の難易度が低いということではなく、受験者は皆、鉄骨製作工場で働いて経験も豊富で、それなりの高い技術レベルにあると思われます。また、資格取得のための勉強も重ねていて、そのため合格率が高いと納得できます。
鉄骨製作管理技術者試験の過去問題集を繰り返し解く
鉄骨製作管理技術者試験の勉強法は、過去問を繰り返して勉強することです。分からないことがあれば、そのたびにテキストで重要な点を調べておきましょう。
ただし、一般的な書店には、過去問題集は販売されていません。さらに、鉄骨製作管理に関する参考書も特殊な分野であることから、探すのが難しいでしょう。
テキスト・問題集については、下記ページで紹介しています。

鉄骨製作管理技術者講習会に参加
鉄骨製作管理技術者講習会に参加することで、鉄骨製作管理技術者教本、建築工事標準仕様書(鉄骨工事)、1・2級鉄骨製作管理技術者試験問題と解説集のテキストが渡されます。
試験問題の解説では、ポイントとなる点の講義も期待でき、全体的に鉄骨製作管理技術者試験のポイントが掴めるのではないでしょうか。