工事現場の安全確保に欠かせないバリケードには、A型やB型、フェンス型など多様な種類があり、用途に応じた選定と設置が求められます。設置時のポイントや事故事例、周辺景観への配慮まで、さまざまな視点から安全対策を考えることが重要です。さらに、CADデータを活用した図面作成は、事前計画や許可申請にも役立ちます。
このページでは、バリケードの種類や設置方法、安全対策に役立つ活用法について解説しています。
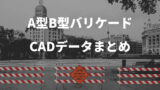
バリケードの種類と選び方~安全にバリケードを設置するために~
工事現場などで工事の区画を伝えるものといえば「バリケード」があります。バリケードにはさまざまな種類があり、基本的には以下の6つに分類されます。
- A型バリケード
- B型バリケード
- フェンスバリケード
- 単管バリケード
- 仮設バリケード
- ガードフェンス
それぞれ特徴が違うので、ひとつずつ見ていきましょう!
A型バリケード

引用元:amazon
最も一般的なの工事バリケードで、高さは約70cm程度、横は1m前後です。
「安全第一」と書かれた黄色と黒色の縞模様のエプロンが付いたA型バリケードは、一度は見たことあるかもしれませんね。
名前の由来からもわかるように、横から見たときにAの形になっていることから、A型バリケードと呼ばれるようになりました。A型バリケードは、現場通路を明確に区画したり、工事車両の可動範囲に人が入らない様に区画するのに適しています。
・折り畳み式で持ち運びやすいが、軽量で飛ばされやすい
・デザインが豊富でシンプルからアニマルモチーフのものまである
B型バリケード
引用元:安全市場
B型バリケードはBバリとも呼ばれる高さ120cm以上で、幅も180cmと大型のものです。
B型バリケードの特徴として、下部が金属で塞がれた作りになっていること、上部がメッシュ状になります。B型バリケードは向こう側が見える作りをしており、A型バリケードとはまったく違う形状です。
工事現場をほぼ遮断できる作りなのもあり、使いやすいバリケードとしても知られています。都会の狭い建築現場や、人通りの多い場所でも使える特徴があります。
また現場の目隠しや飛散物防止にも使え、都会の狭い道路沿いの建設現場や人通りの多い道との遮断に有効です。
・下部は金属で上部はメッシュ状
・使いやすいバリケードとして知られている
フェンスバリケード

引用元:日本機電株式会社
B型バリケードと同様の形をしていて板など、仕様にさまざまなパターンがあります。
例えばオールメッシュなら風の強い環境で、全面メッシュ、全面金属も倒れにくく、全面ガルバリウムタイプなら防錆力に優れ美観を損ねないという特徴があります。丈夫な作りになっているフェンスバリケードは、風が強い場所での作業にも向いています。
専用キャスターを付けることで移動式にすることも可能で、ゲートの代わりとしても使用することができます。なかにはカラフルなどデザインにこだわっているものもあるので、設置環境にこだわっている現場にもおすすめです。
・メッシュは丈夫な作りになっていて風に飛ばされにくい
・ガルバリウムタイプは防御性に優れ美観を損ねない
単管バリケード

引用元:ソニテック通販サイト
単管と呼ばれるパイプをバリケード用にアレンジしたもので、パイプの太さが48.6mmと決められているバリケードです。太さには規定がありますが、長さは規定がなく長くても短くてもOKです。
A型バリケードに似ている特徴のある単管バリケードですが、街のなかでもさまざまな場所で見かけます。ペンギンやサル、カエル、キティちゃんなどのバリケードは一度見たことがあるのではないでしょうか。
単管バリケードは、アレンジのしやすさが魅力的です。例えばパイプを2本あるいは3本使い、両端をA型のプラスチック製の脚で固定することで、A型バリケードと同じような形状になります。
・ペンギンや変えるなどのキャラクターデザインが流行っている
・パイプの長さを調節すればさまざまな使い方ができる
仮設バリケード

引用元:イプロス
仮設バリケードは工事で仮囲いをするときに使用するものです。広い範囲の作業でも仮囲いバリケードなら圧迫感がなく、整然と並んでいる姿はすっきりとみえます。
また仮設バリケードを建てることで周囲の住宅への配慮にも繋がることから、企業PRなどで使われていることも多いです。企業としての「顔」の役割も担っており、仮設バリケードも組み合わせ次第で使い方が変わるのが特徴的ですね。
・使用時に圧迫感は少なく、周囲の住宅にも配慮している
ガードフェンス
引用元:カワモリ産業
ガードフェンスは、工事現場で人の立ち入りを制限したいときにも使えます。ガードフェンスは気軽に使えること、持ち運びの利便性にも定評があり、工事現場などで必ず見かけるのがガードフェンスといっても過言ではありません。
・工事現場では必ずといっていいほど使用されている
キャラクターバリケードの元祖は「サル」!
ペンギンやキティちゃんなどあらゆるキャラクターのバリケードがありますが、その元祖は実は北海道旭川市で使用された「サル」がキャラクターデザインの始まりなのです。
そもそも、こうしたキャラクターデザインの単管バリケードを初めて製造したのは、主に保安用品のレンタルをしている「仙台銘板」という仙台の会社です。その仙台銘板が旭川市より依頼されてサルのバリケードを作ったのが、キャラクターバリケードの始まりでした。
今ではサル以外にもさまざまな動物、キティちゃんなどのキャラクター、ご当地にちなんだものなど、多種多様なキャラクターバリケードがあります。
バリケードを設置するうえでのポイントや注意点

バリケードの設置方法を決める寸法選び
バリケードの寸法を決めるうえで、どのぐらいのサイズ感のものを選べばいいのか迷っている人もいると思います。そもそもバリケードによる違いもありますし、それぞれの特徴や設置方法などの含めて決めなくてはいけません。
例えば視覚性を重視したものや、積載時に配慮した積み重ねができるバリケードなどもあります。到来品と比較したときに耐寒性や耐久性を向上したもの、安全性に配慮し丸みのあるフォルムのバリケードなど、企業によってさまざまな工夫をしています。
そのため、バリケードに何を求めるのかによって、この辺りの違いにも注意したいものです。バリケードの寸法は、もともと規格で決められているものも多く上限があります。幅が広い範囲での工事では、バリケードを複数使うなどして調整する必要もあります。
単管を使って行うバリケードだと、長さを変えれば寸法が調整できる場合もありますが、もともとのバリケードよりも重いものだと倒れてしまう危険性にも配慮して設置方法を考える必要があります。
バリケードをどこに使うのかをしっかり考えよう
寸法による違いもありますが、バリケードを安全に使うための設置方法も考えなくてはいけません。工事現場と通路の境界に設置するのはもちろん、工事現場全体を囲み、関係者以外が入場しないようにするために使うこともあります。
使える場所はさまざまで、廃棄物置の区画を示すものや、重機を使用するときの安全対策を、バリケードで行うこともあります。使うバリケードによっても違いますが、公共工事では規格にあった安全機材を使用しなくてはいけないなどの決まりもあります。
基準が満たされないままで工事を行って、なにかあった場合は大きな責任が求められてしまいます。バリケードを使用する場合、寸法や形状をしっかりと確認して認識するための工夫も必要になります。
また、最適なバリケード選びができるかによっても、工事を円滑に進めるための大きなポイントになります。もしもを考え近隣とのトラブルを防止する、プライバシーを守るなどバリケードを目的からも選ぶようにすると、失敗しないバリケードの設置に繋がるはずですよ。
バリケードや目印にカラーコーンを使ってもいいの?
工事バリケードとして代用されやすいのがカラーコーンです。軽くてよく目立ち、安価であることから、店舗の順番待ちの際の誘導や、「徐行」「P(駐車場)」「一方通行」などの臨時の標識として使われることがよくあります。カラーコーンの間にバーを渡せば簡易的な区画整理をすることもでき、何かと重宝します。
ただ、あくまで簡易的な措置としては好まれますが、「強風などにより倒れやすい」「バーが外れやすい」「簡単に乗り越えられる」といったバリケードとして常時使用するには問題がありそうな部分も。
また近年の温暖化現象に伴い、アスファルトの熱でカラーコーンが変形してしまうケースも問題視されています。塩化ビニルの素材は耐熱温度が60~80度とあまり高くないため、屋外で夏に使用するには塩化ビニルよりも高密度ポリエチレン製のカラーコーンをおすすめします。
建築・道路工事用安全機材の分類や必要性
工事用安全機材は、建築・土木などの工事現場で、安全を確保するために用いられる保安用品です。それでは建築工事と道路工事別に、工事用安全機材の分類や必要性と使用することの利点について説明しましょう。
建築工事
以下は主な建築工事用の安全機材です。
- 工事用看板
- ガードフェンス
- バリケード
- 工事保安灯
工事用安全機材のCADデータをビルの建築現場、化学プラントの建設、ダムの土木工事などの現場では、必ず工事用安全機材が使用されます。これらを活用することで、施工要領書を分かり易くして、より安全な工事を行えます。
道路工事
以下は主な道路工事用の安全機材です。
- 方向指示版
- 回転灯
- 電光表示器
- カラーコーンやコーンバー
- 衝撃吸収緩和剤
- ブロック
工事計画書や工事申請書の工事説明図にCADデータを使用して安全機材の配置を表すと、チェックする人が詳細に確認できます。
例えば道路工事では、周囲と作業者への安全を確保してから工事するために、カラーコーンや仮設フェンスで工事エリアを囲い、交通規制帯を設け工事箇所の隔離などを行います。
この交通規制帯の配置が悪いと渋滞が起こりやすくなるため、現場状況を十分に調査しなくてはいけません。
その配置計画を分かり易く表現するためにもCADデータを用いた工事計画書を、フリーでも有料でもいいのでダウンロードして利用しましょう
バリケードの事故事例と気をつけるべきポイント
工事バリケードやフェンスの役割は、工事現場への立ち入りを制限し、現場と通行人両方の安全を図ることです。これまで起きた事故の事例をもとに、今の現場でのフェンスの設置方法が本当に安全かどうか、今一度考えてみましょう。事故の事例は判例集などを参考にしています。
事例①「歩行者がバリケードの内側に侵入して開口部に転落」
過失割合をもとめ裁判になりましたが、その際裁判所は、現場の場所が市街地で人通り車通りが一定量あったことを踏まえ、照明の設置や高いフェンスの設置の義務について言及しています。
実際に建設会社が設置していた予防策は高さ80センチのバリケード、点滅灯火、立て看板で、それでは不十分という結論となり、建設会社は25パーセントの過失となりました。
こうした事故の場合、建設会社側の設置方法にルール上誤りがなければ過失の責任は無し、あるいは軽微と判断されます。特にバリケードの高さ、照明の有無が重要になることが分かっていただけると思います。
事例②「A型バリケードが強風で倒れ、通行車両が損傷」
事故当日は雨天のため作業はしておらず、夜20時ごろ、強風でA型バリケードが倒れ、そこに走行してきた一般車両が乗り上げ、車体の下回りを損傷する事故となりました。
当日は暴風雪警報が発令されていました。
考えられる対策
- 強風に対する転倒防止策として重石を付ける
- バリケードを連結させる
事例③「開口部から作業員が転落、死亡した」
13メートルの開口部から作業員が誤って転落し死亡しました。
この時作業員は安全帯を付けていませんでした。
安全帯の装着による転落・墜落防止策の徹底がされていなかったことに加え、開口部はベニヤ板での養生とカラーコーンを置いたのみの簡易的な立ち入り防止策しかなかったことが事故発生の原因であると判断されました。
現場代理人は労働安全衛生法違反の疑いで地方検察庁に書類送検されました。
事故の後、この現場では伸縮装置が設置され開口部がなくなった後、作業足場が確保できた段階からも安全帯を使用することを徹底しました。
また是正勧告を受け、工事従事者全員に対して安全管理の徹底と作業手順の再確認を行い、翌日には是正措置を検討、対策を行ったとのことです。
考えられる対策
- 開口部にはカラーコーンだけでなくバリケード
- ネット覆いコーンバーなどを使用すること。
- 夜間の関係者以外の侵入防止のためバリケード用看板を立てかける
- バリケードを強化することなどが挙げられます。
バリケードによる現場の安全対策
工事現場での安全対策には、「現場内の安全確保」と「現場周辺の安全確保」という大きな二つのポイントがあります。それぞれ問題点をまとめてみました。
工事現場「内」での安全の確保
作業工程毎に作業員や搬入資材が変わるため、安全対策の徹底が重要な課題になります。
それぞれの動線が交錯することのない、安全な作業計画を作成・徹底・実行する工夫が必要です。
ヒヤリハット事例などの情報共有も、事故を防ぐツールのひとつです。
工事現場「周辺」での安全確保
工事現場にはさまざまな工事用、資材運搬、廃棄物運搬用の車両などが出入りします。
道路工事などでは、現場のすぐ近くを歩行者、通行車両などが通過する状況になります。
そのため、安全対策の地域住民へのアピールも大事な仕事です。
住民への説明ツールの一つとして、バリケードのCADデータを活用してみましょう。
フリーのデータでもじゅうぶん使えますよ。
バリケードで安全確保するための注意点
安全対策はハードとソフトの両面で
バリケードなどの安全資材がハード面、安全計画をソフト面とし、その両面から安全確保を行うことで事故防止につながります。
近年では国土交通省も安全計画の立案だけでなく、組織的な取り組み方を評価しています。
作業員に安全計画を徹底するため、資料やポスターなどにバリケードの2D・3DCADデータを活用すると効果的です。
現場内でバリケードを使用する際の注意点
障害物や重機可動域を図面や現地で確認し、幅や高さの両方で干渉しない配置にしましょう。
施工の手順や安全管理の手段をわかりやすく説明する資料を作成し、新規入構者含めて作業員に周知徹底を図ってください。
他の工事現場での工夫例、ヒヤリハット事例なども参考にして、作業員の間で情報を共有しましょう。
工事現場周辺の安全確保のための注意点
歩行者通路を設ける場合は歩行者が通行時に迷わないよう、保安灯またはセーフティコーンを用いて通行ルートや信号待ちの待機場所をはっきり示しましょう。
必要な情報が歩行者、ドライバーの目に入るよう、重要度を考えて配置してください。
CAD図面や現地で、バリケードなどが歩行者や通行車輌の妨げになっていないかを確認しましょう。
周囲景観にも配慮したバリケード
大型で現場の外観を構成するB型バリケードは、A型バリケードや誘導案内看板を引き立たせるデザイン・色を選んでください。
設置方法が簡単で丈夫だとなお良いです。
B型バリケードは、上部にメッシュシートなどを使い、閉塞感のないデザインにすると現場のイメージアップにもつながります。
必要に応じて街の背景と一緒にCADデータを配置し、バリケードの配色や雰囲気などを確認しましょう。
バリケードのCADデータで現場内外の安全対策を
工事計画作成時には多くの関係者にわかりやすく説明しなくてはなりません
そんなときにこのバリケードCADデータを使って、視覚に訴える資料を作成することで、資料作成もプレゼンも効率よく進められるのではないでしょうか。
バリケードを使った安全計画の立案
現場内の危険範囲に作業員や車両が近づかないよう、バリケードなどで動線を分離すること。
安全計画はすべての作業員にわかりやすく作成し、周知徹底を促してください。
歩行者には色や配置でわかりすく歩道や待機場所を知らせましょう。
安全のために必要な情報は目立つようにしながら、街の雰囲気にも配慮しましょう。
事故や近隣住民からのクレームは工期遅延、工事原価の悪化、工事成績の低下の原因になります。
バリケードの2D・3DCADデータをうまく利用して視覚に訴える資料を効率よく作成し、安全な現場運営を行っていきましょう。
安全対策に必須。バリケードのCADデータの必要性
工事計画書の添付図面には不可欠なA型バリケードやB型バリケードのCADデータ。
これらの必要性について、より詳しく解説していきます。
仮設バリケードの設置寸法を考えるときはcadデータを使った図面が便利
バリケードを設置する必要がある時は、あらかじめ工事計画書などの書類提出の際に位置や設置する数などを決めておかなければいけません。一体、どこに、いくつ、どんな仮設バリケードを設置すれば良いのか…規定と見比べながら考える必要がありますが、そこで役立つのがcadデータを使った図面です。
図面上で仮設バリケードの設置寸法を検討することで、いざ現場で設置しようというときに大きすぎる、長すぎる、逆に少なすぎた……といったミスを減らすことができます。
CADデータの有効利用は、注意喚起や安全対策に効果的
A型バリケード、B型バリケードのCADデータは、メーカーサイトやリース会社のホームページだけでなく、フリーCADはダウンロードサイトなどにも数多く存在しています。そのため使用の際には用途に応じて、CADデータを選定していく必要がありますね。
特に安全労務用の書類の添付図や、公共工事の提出用図面においては、使用するバリケードの形状や寸法を正確に記載した図面が必要となる事があります。その際は、実際に使用するメーカーや、リース会社が提供しているCADデータを利用すると良いでしょう。
また3DCADデータは視覚的にもわかりやすいので、工事の安全対策を地域住民に説明する際に、添付資料として利用できます。工事に携わる作業員の注意喚起に、ポスターや表示物に利用すると大変有効です。
A型バリケード、B型バリケードCADデータの利用方法
ここでは、A型バリケード、B型バリケードCADデータの利用方法、道路占用許可の資料作成、施工ヤ-ドの必要範囲のシュミレ-ション、説明のしやすい施工計画図を作成する方法などについて紹介しています。
1. バリケードのCADデータで、道路占用許可資料の作成
A型バリケード、B型バリケードのCADデータは、道路の路上工事おける占用許可資料作成に活用できます。
例えば、工事の安全対策を、A型バリケード、B型バリケードのCADデータを活用することにより視覚的に表現できます。
また、道路を占用する位置や大きさを、詳細に表現することができます。
そのため、道路管理者へ道路占用許可の申請をする際に、正確に分かりやすく伝えることができるようになります。
2. 施工ヤードの必要範囲をバリケードでシミュレーション
A型・B型バリケードのCADデータは、施工ヤードの必要な範囲の検討において活用でき、施工ヤードの周りには、ほとんどの場合、バリケードを設置し安全対策を図ります。
その際に、正確なバリケ-ドの大きさを表現することによって、詳細な施工ヤードの必要範囲を表現できます。例えば、道路の路上にて施工ヤードを設置する際には、現況の車道幅員がどのくらい残るのかという点が重要になります。その幅員を正確に表現することによって、発注者との協議が円滑に進みます。
また、施工ヤードを借地によって確保する場合においても、正確なバリケードの大きさを表現することにより、必要最小限の借地で済むこともできます。
工事バリケードのcadデータはフリーダウンロードがおすすめ
工事現場におけるバリケードの設置はとても重要であり、誤ったデータを元に作成すると命に係わる事故に繋がります。まずはどんなCADデータがあるのかを知って、施工図面に必要なものをダウンロードしてみましょう。
ネットで無料でダウンロードできるものもあり、好みのファイル形式を探すのも簡単です。図面に使用したり、設置寸法を落とし込むことができれば、作業効率を格段に上げることができますよ!
